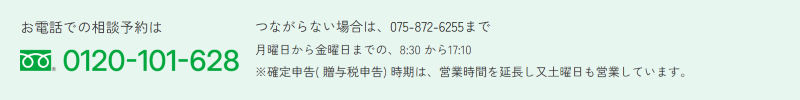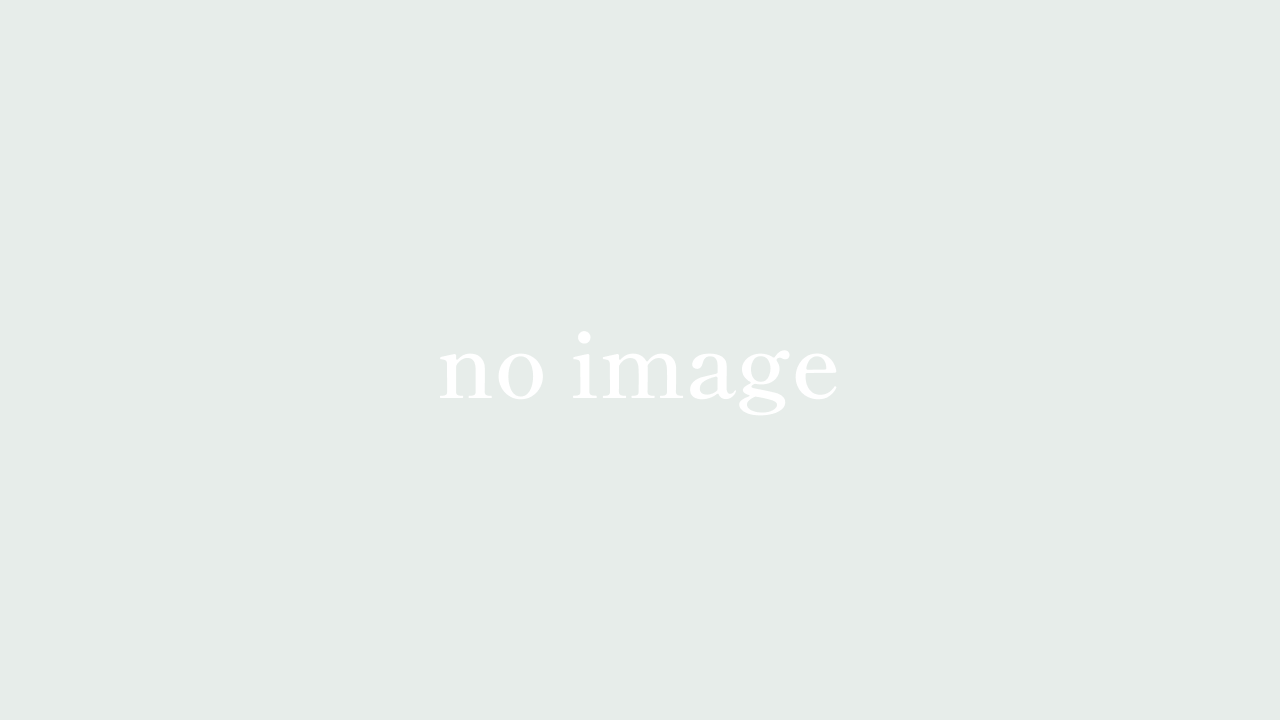【税理士が解説】相続税申告の必要書類・添付書類(ケース別)一覧・取得方法・効率的に集める方法
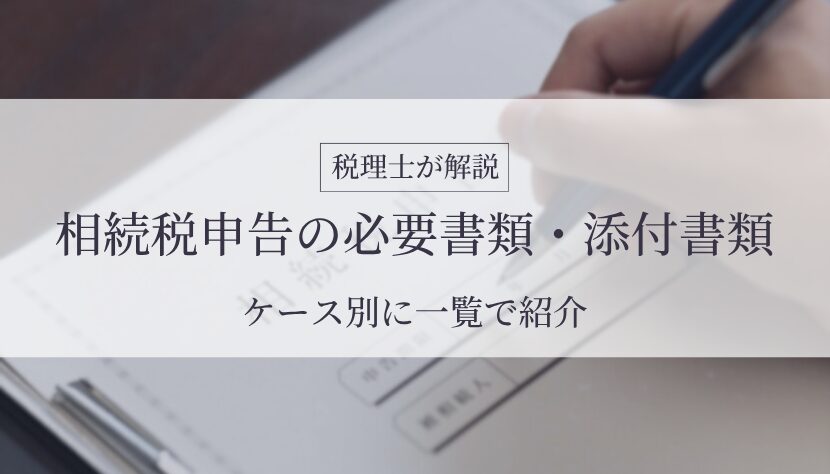
相続税申告の必要書類は全員に共通するわけではなく、相続の状況や財産の種類で大きく違います。
日常生活では馴染みのない書類も多く、何をどのように集めればよいかわからない方も多いでしょう。
本記事では、相続税申告の必要書類・添付書類をケース別に解説します。
取得方法や手数料も併せてまとめているので、一覧で確認したい方はぜひご覧ください。
 |
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
相続税申告の必要書類【一覧表】
相続税申告の必要書類は、大きく以下3つに分かれます。
| ・相続税申告書 ・相続人全員の本人確認書類の写し ・相続税申告書の添付書類 |
本人確認書類の写しは、マイナンバーの番号と身元を確認するために提示または添付が必要で、e-Taxを利用して申告する場合は不要です。
具体的には、以下のものが本人確認書類として認められます。
※通知カードの氏名や住所が住民票と同じ場合に限り、番号確認書類と身元確認書類として利用できる
| 番号確認書類 (以下のいずれか) |
・マイナンバーカードの裏面 ・通知カード ・マイナンバーが記載されている住民票 など |
| 身元確認書類 (以下のいずれか) |
・マイナンバーカードの表面 ・運転免許証 ・身体障害者手帳 ・パスポート ・在留カード ・公的医療保険の被保険者証※保険者番号・被保険者等記号・番号部分を復元できない程度に塗り潰したもの など |
相続税申告の添付書類は、次章でケース別に解説します。
前提として、税務署にすべてを提出しなければならないわけではなく、実際にどの書類を添付すべきかは税理士の判断に任せましょう。
ケース別:相続税申告の添付書類一覧
ここからは、相続税申告の添付書類を以下の順に紹介します。
| ・原則必要なもの ・相続税の特例・控除を適用するケース ・現金・預貯金を相続するケース ・不動産を相続するケース ・有価証券を相続するケース ・死亡保険金が支払われたケース ・その他の財産を相続したケース ・債務・葬式費用を控除するケース ・生前に贈与を受けているケース |
原則必要なもの
相続税申告書に添付する書類の中で、原則必要なものは主に以下が挙げられます。
なお、令和6年3月1日から、本籍地が遠方にある場合でも最寄りの市区町村役場で戸籍謄本等を取得できるようになりました(戸籍謄本の広域交付制度)。
広域交付で戸籍謄本等を取得できるのは、直系尊属(本人、配偶者、父母、祖父母など)と直系卑属(子、孫など)に限られます。
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 被相続人と相続人全員の戸籍謄本等 (または法定相続情報一覧図の写し) |
最寄りまたは本籍地のある市区町村役場 (法務局) |
○ (×) |
300〜450円程度 (無料) |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人が最後に住んでいた地の市区町村役場 | ○ | 300円程度 |
| 相続人全員の住民票 | 相続人が住んでいる地の市町村役場またはコンビニ | ○ | 300円程度 |
※相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの
また、状況に応じて以下の書類も準備が必要です。
| 相続の状況 | 必要書類 | 取得場所 |
| 遺言書がある | 遺言書の写し | 手元にあるもの |
| 遺産分割協議書がある | 遺産分割協議書の写し/相続人全員の印鑑証明書 | 作成したもの/相続人が住んでいる地の市町村役場またはコンビニ |
| 未成年の相続人がいる | 特別代理人選任の審判の証明書 | 選任時に裁判所から発行されたもの |
| 相続放棄した相続人がいる | 相続放棄受理証明書 | 被相続人が最後に住んでいた地を管轄する家庭裁判所 |
| 申告期限内に遺産分割ができない | 申告後3年以内の分割見込書 | 国税庁のホームページ |
相続税の特例・控除を適用するケース
適用する特例や控除によって添付書類が異なるため、ここでは代表的な「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」のケースを紹介します。
なお、同じ書類は重ねて取得する必要はありません。
▼配偶者の税額軽減
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 被相続人と相続人全員の戸籍謄本 (または法定相続情報一覧図の写し) |
最寄りまたは本籍地のある市区町村役場 (法務局) |
○ (×) |
300〜450円程度 (無料) |
| 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し | 手元にあるもの | ― | ― |
| 相続人全員の印鑑証明書 ※遺産分割協議書がある場合 |
相続人が住んでいる地の市町村役場またはコンビニ | ○ | 300円程度 |
| 申告期限後3年以内の分割見込書 ※申告期限内に分割できない場合 |
国税庁のホームページ | ○ | 無料 |
▼小規模宅地等の特例
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 被相続人と相続人全員の戸籍謄本 (または法定相続情報一覧図の写し) |
最寄りまたは本籍地のある市区町村役場 (法務局) |
○ (×) |
300〜450円程度 (無料) |
| 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し | 手元にあるもの | ― | ― |
| 相続人全員の印鑑証明書 ※遺産分割協議書がある場合 |
相続人が住んでいる地の市町村役場またはコンビニ | ○ | 300円程度 |
| 申告期限後3年以内の分割見込書 ※申告期限内に分割できない場合 |
国税庁のホームページ | ○ | 無料 |
※加えて、以下の区分に応じた書類の添付が必要
| ・特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等 |
上記特例の詳細は、国税庁のホームページで確認できます。
現金・預貯金を相続するケース
現金・預貯金を相続するケースでは、主に以下の書類を添付します。
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 残高証明書 | 金融機関 | 金融機関による | 1,000円前後 |
| 既経過利息計算書 | 金融機関 | 金融機関による | 2,000円前後 |
| 通帳の写し (または預金取引履歴) |
手元にあるもの (金融機関) |
― (金融機関による) |
― (1,000円前後) |
金融機関によって即日発行の可否や手数料の金額に差があるため、事前に確認しておくと安心です。
不動産を相続するケース
不動産を相続するケースでは、主に以下の書類を添付します。
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 登記事項証明書 (登記簿謄本) |
法務局 | ○ ※郵送の場合は× |
600円 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産が所在する市町村役場 | ○ ※郵送の場合は× |
300円程度 |
| 名寄帳(固定資産課税台帳) | 不動産が所在する市町村役場 | ○ ※郵送の場合は× |
300円程度 |
| 公図または地積測量図 | 法務局 | ○ ※郵送の場合は× |
450円 |
| 住宅地図 | インターネット等 | ○ | 無料 |
| 賃貸借契約書 ※賃貸物件を借りている場合 |
手元にあるもの | ― | ― |
郵送の場合は、手元に届くまで1〜2週間程度かかります。
なお、登記事項証明書等をオンラインで申請すると、手数料が安くなります。
オンラインで申請を行い、郵送で受け取ると500円、最寄りの法務局または法務局証明サービスセンターで受け取ると480円です。
詳細は、以下を確認してみてください。
法務局:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
有価証券を相続するケース
有価証券を相続するケースでは、主に以下の書類を添付します。
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 取引残高報告書 | 手元にあるもの | ― | ― |
| 配当金支払通知書 | 手元にあるもの | ― | ― |
| 直近3期分の決算書 ※非上場株式の場合 |
証券会社 | 証券会社による | ― |
死亡保険金が支払われたケース
被相続人の死亡保険金が支払われたケースでは、主に以下の書類を添付します。
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 支払通知書 | 保険会社 | 保険会社による | ― |
| 保険証書 | 手元にあるもの | ― | ― |
| 解約返戻金がわかる書類 | 保険会社 | 保険会社による | ― |
その他の財産を相続したケース
現金・預貯金や不動産、有価証券等以外の財産を相続したケースでは、主に以下の書類を添付しましょう。
| 財産の種類 | 必要書類 | 取得場所 |
| 退職金 | 支払通知書 | 被相続人の勤務先 |
| 自動車 | 車検証のコピー | 手元にあるもの |
| ゴルフ・リゾート会員権 | 預託金証書 | 手元にあるもの |
| 貸付金・前払金等 | 金銭消費賃借契約書または残高がわかるもの | 手元にあるもの |
| 骨董品・貴金属等 | 鑑定書 | 手元にあるもの |
債務・葬式費用を控除するケース
被相続人の債務や葬式費用は、相続財産から控除できます。
添付する書類は、主に以下の通りです。
▼債務
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 借入残高証明書 | 金融機関 | 金融機関による | 1,000円前後 |
| 金銭消費貸借契約書 | 借入先 | 借入先による | ― |
| 未納租税公課の領収書 | 手元にあるもの | ― | ― |
| 未払金の領収書 | 手元にあるもの | ― | ― |
▼葬式費用
| 必要書類 | 取得場所 | 即日発行 | 手数料 |
| 領収書 | 手元にあるもの | ― | ― |
| お布施・心づけ等の記録 | 手元にあるもの | ― | ― |
葬式費用の領収書等は、手元に保管しておきましょう。
生前に贈与を受けているケース
被相続人の生前(相続開始前3〜7年以内)に贈与を受けた財産は、相続税の対象となります。
添付する書類は、主に以下の通りです。
| 相続の状況 | 必要書類 | 取得場所 |
| 過去3年以内に贈与を受けた | ・贈与契約書 ・過去3年分の贈与税申告書(控) |
手元にあるもの |
| 相続時精算課税制度を適用した | ・贈与契約書 ・選択時以降の贈与税申告書(控) ・相続時精算課税制度選択届出書 ・被相続人の戸籍の附票の写し |
手元にあるもの ※被相続人の戸籍の附票の写しのみ、最寄りまたは本籍地のある市区町村役場 |
| 教育資金の一括贈与/住宅取得等資金の贈与/結婚・子育て資金の一括贈与を受けた | ・贈与契約書 ・贈与税申告書(控) ・非課税申告書(控)(※) ・管理残高がわかる資料 |
手元にあるもの ※教育資金の一括贈与/結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税申告書のみ、金融機関 |
※教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合は、金融機関発行の非課税申告書を添付
なお、生前贈与の加算対象期間が見直され、令和6年1月1日から相続開始前3年以内が7年以内に延長されています。
以下の期間に取得した財産は、相続財産に含めましょう。
| 令和6年1月1日〜令和8年12月31日に相続が開始した場合 | 相続開始前3年間 |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日に相続が開始した場合 | 令和6年1月1日〜相続開始日 |
| 令和13年1月1日以降に相続が開始した場合 | 相続開始前7年間 |
相続税申告の必要書類を効率的に集める方法
相続税申告の必要書類は、以下の順に揃えると効率的です。
| 1.身分を証明する書類 2.発行に時間がかかる書類 3.自宅に保管している書類 |
詳しく解説します。
1.身分を証明する書類
戸籍謄本等はその他の書類を取得する際に提出が求められるため、最初に揃えておくのがおすすめです。
なお、被相続人の戸籍謄本等は出生から死亡までのものを取得しましょう。
過去に本籍地が変更されているとすべて揃えるまで時間がかかる場合もありましたが、令和6年3月1日に戸籍謄本等の広域交付制度が開始されたことにより、以前と比べて揃える手間は減るかもしれません。
2.発行に時間がかかる書類
金融機関や保険会社などで発行の申請が必要な書類は、手元に届くまで時間がかかることを踏まえて手続きを行いましょう。
遅ければ、2週間前後の時間がかかる場合も多いためです。
3.自宅に保管している書類
各種証明書や領収書など自宅に保管しているものは改めて取得する必要はありませんが、すぐに提出できるよう整理しておきましょう。
もし見当たらなければ再発行の手続きが必要な場合もあるため、早めに確認しておいてください。
相続税申告の必要書類に関するよくある質問
最後に、相続税申告の必要書類に関するよくある質問にお答えします。
相続税申告に通帳のコピーは必要?
税務署に通帳のコピーを提出する義務はありませんが、財産の申告漏れを防ぐために確認は必要です。
なお、税務署は被相続人や家族の預貯金残高・入出金履歴を確認できるため、申告時は通帳の内容も把握したうえで正しく申告しましょう。
相続税申告は自分でできる?
相続税申告は自分でもできますが、税理士に依頼せず申告する人は少数です。
相続財産ごとに多くの書類を集める必要があるほか、財産の評価や税額の計算には専門知識が求められます。
税額も負担も最小限に抑えるには、相続に強い税理士へ依頼するのが賢明です。
詳しくは、以下の記事で解説しています。
必要書類は税理士に集めてもらえる?
税理士は、職権により他人の戸籍や住民票を取得できます。
以下のような場合は、税理士に依頼するとよいでしょう。
| ・相続人が忙しい ・高齢で取得が難しい ・申告期限が近い など |
上記を除けば、自分で集めたほうが税理士への依頼費用を抑えられます。
相続税申告のご相談は税理士法人吉本事務所へ

相続税申告のご相談は、税理士法人吉本事務所へお問い合わせください!
当事務所の相続専門税理士が、100件以上の申告実績をもとにお客様の有利な申告をサポートいたします。
申告書を作成するには必要書類を集めるだけでなく、被相続人の相続財産を調査したり現金以外の財産を評価したりなど、多くの作業を段階的に進めなければなりません。
お客様のご状況に合わせて限りなく負担を軽減できるようご提案いたしますので、相続税申告に関するお悩みはぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所のホームページはこちらから
無料お見積り・お問い合わせはこちらから
まとめ
相続税申告の必要書類・添付書類は、相続の状況や財産の種類で異なるため、自身のケースと照らし合わせながら準備を始めましょう。
申告期限は10か月までと短いことから、以下の順で効率的に集めることがポイントです。
| 1.身分を証明する書類 2.発行に時間がかかる書類 3.自宅に保管している書類 |
なお、申告期限に遅れると、相続税を抑える特例や控除が適用されないほか、本税に延滞税が加わり、相続人の負担が大きくなります。
もし不安な場合は、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。