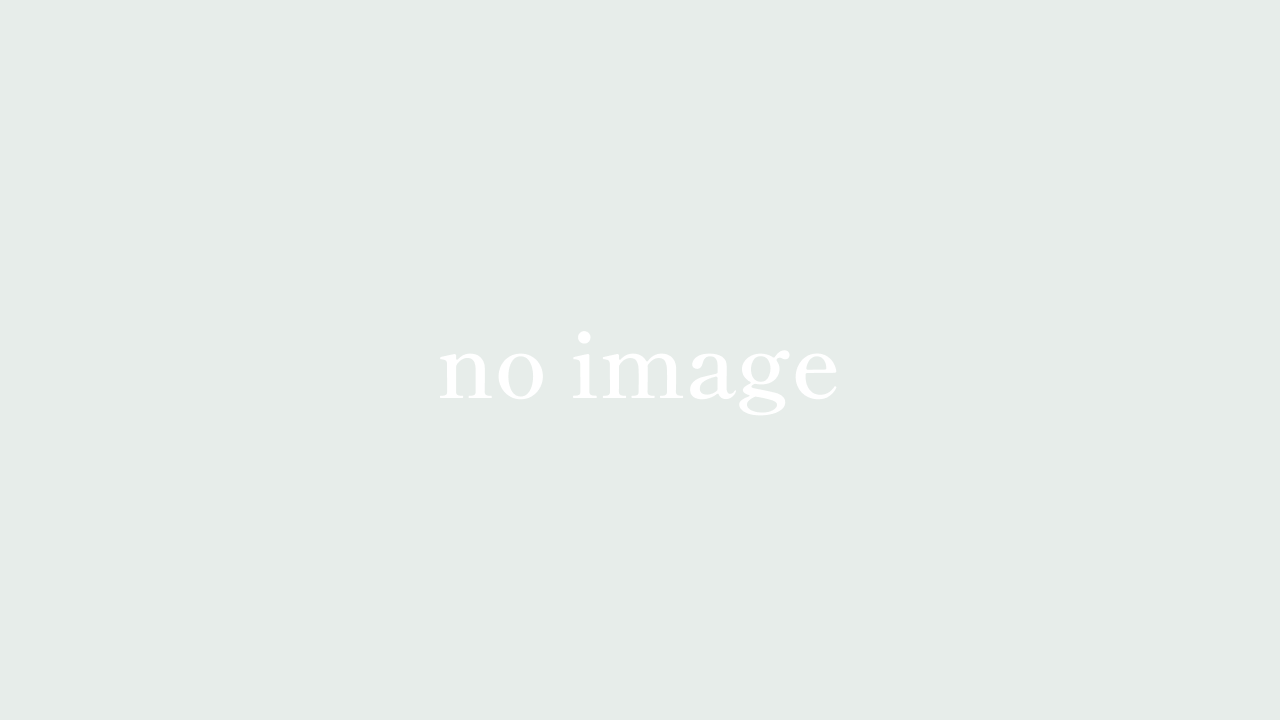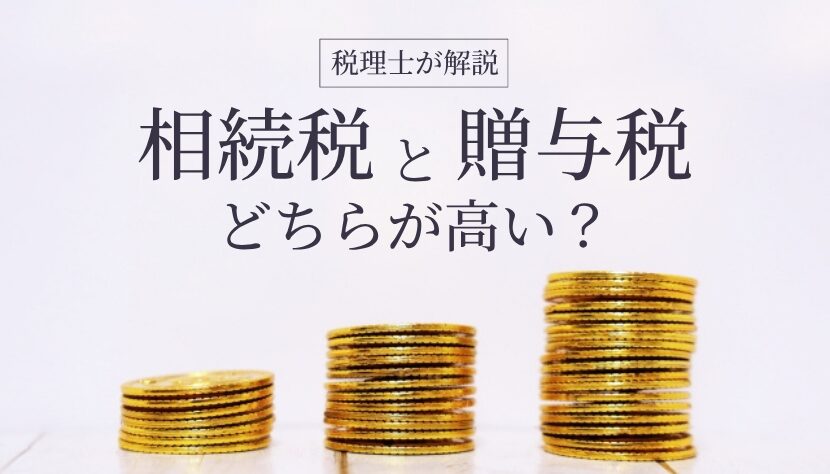住宅取得等資金の贈与税の非課税のまとめ(令和2年8月)
1.住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
この制度は、父母や祖父母から、子供や孫に住宅の取得をするための金銭を贈与した場合に、一定の金額までは贈与税がかからないようにしてあげましょうという制度です。
2.非課税限度額
(1)消費税10%の場合
| 契約日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
| 平成31年4月1日〜令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 令和2年4月1日〜令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 令和3年4月1日〜令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
(2)(1)以外の場合
| 契約日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
| 〜平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成31年4月1日〜令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 令和2年4月1日〜令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
| 令和3年4月1日〜令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
個人間の中古住宅の売買の場合には、原則として消費税がかかりませんので、(2)に該当します。
また、「省エネ等住宅」とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上」のいずれかを満たす住宅をいいます。
3.適用を受けるための要件
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を受けるためには、次の要件の全てを満たす必要があります。
(1)祖父母や父母といった直系尊属から子や孫への贈与であること。
(2)贈与を受けた子や孫が、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3)贈与を受けた子や孫の合計所得金額が2000万円以下であること。
(4)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
(5)2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(6)配偶者、親族などの特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしていないこと。
(7)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築や増改築、新築のための土地の取得をすること。
(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または遅滞なく、その家屋に居住することが確実であると見込まれること。翌年12月31日が期限となります。
(9)住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、床面積の2分の1以上が受贈者(贈与を受けた子や孫)の居住用であること。
(10)住宅用の家屋が日本国内にあること。
(11)贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど、一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出をすること。
4.注意点
次のような場合には、特例の適用が受けられなくなりますので、注意して下さい。
(1)贈与のあった年の翌年3月15日までに住宅が完成しない場合
工事が完了に準ずる状態にある場合を除き、原則翌年3月15日に住宅の引き渡しがされていない場合には、適用が受けられません。
契約から完成までに時間がかかるといった場合には、契約のタイミングではなく、残金を支払う引き渡し時に贈与を受けるなどの検討が必要です。
(2)贈与のあった年の翌年12月31日までに住んでいない場合
翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできないため、修正申告をして、贈与税の納付をする必要があります。
(3)住宅ローンの決済後に贈与を受けた場合
贈与により取得した資金を直接住宅の取得に充てるのではなく、住宅ローンの返済に充てた場合には、適用が受けられません。
5.小規模宅地等の特例との関係
「小規模宅地等の特例」とは、相続税の計算上、自宅の評価額を330㎡まで8割減できるという大変お得な制度です。
被相続人の自宅を相続したときに、この特例が適用できるのは、配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかとなります。
住宅を新築や取得してしまうことで、将来相続があったときに「家を持っていない親族」に該当しないこととなり、小規模宅地等の特例が受けられなくなりますので、相続財産が多いことが分かっている場合には、相続税額のシミュレーションなどもしておいた方が安心です。
6.特例の非課税限度額以上に贈与をしたい場合
この特例では契約日や家屋の種類によって、非課税限度額が決まっています。
もし、その非課税限度額以上に贈与をしたい場合にはどうしたらよいでしょうか。
もちろん、非課税限度額を超えた部分について贈与税を支払えば、いくらでも贈与をすることは可能です。
しかし、贈与税の税率は1000万円を超えると40%以上と大変高く、せっかく子や孫に贈与をしたいと思っても、半分近くを税金で持っていかれてしまうということになります。
そこで、税負担を押さえて、贈与をするための方法をいくつかご紹介します。
(1)暦年贈与
贈与税では110万円の基礎控除額というものがあります。
つまり、毎年110万円までは税金を払わずに贈与することができます。
毎年110万円ずつ贈与をするだけという最も手軽でポピュラーな方法ですが、大きい金額を贈与したい場合には時間がかかってしまうのが難点です。
(2)相続時精算課税制度
もし、暦年贈与では時間が足りないといった場合には、相続時精算課税制度を使う方法があります。
これは、2500万円まで贈与税はかからない代わりに、将来相続があったときに相続税が課税されるという制度になります。
2500万円超えた部分は一律20%で課税されます。
相続税の基礎控除額は大きいため、相続税がかからない家庭も多く、そうした場合には大変お得な制度といえます。
しかし、一旦相続時精算課税制度を選択すると、その後は暦年贈与の110万円を利用することができなくなってしまうため、相続税がかかる場合にはデメリットも大きく、安易に利用することは危険です。
この制度を選択する場合には、相続税額のシミュレーションも行って、慎重に行う必要があります。
(3)贈与者との共有名義
取得する住宅を贈与者(親や祖父母)との共有名義にするという方法もあります。
これは、相続時精算課税制度と同じような効果があります。
共有名義の内、贈与者の取得部分については、相続で受贈者(子や孫)が取得することで、今回贈与税の対象とはならず、将来の相続税の対象となり、節税の効果があります。
相続税は基礎控除額が大きく、贈与税より税率も低いこと、家屋は時間が経つにつれて、価値が減少することなどから、税負担が抑えられます。
他にも相続人がいる場合には、遺言を残すことで、住宅の取得者である子や孫に確実に相続させることができます。
遺言がない場合には、相続人の共有名義となって、権利関係が複雑となったり、相続人でない孫の場合にはそもそも取得できなかったりといったことが起きてしまいますので、注意して下さい。
7.まとめ
この非課税制度は基本的に非常に良い制度です。
税負担を押さえて、子供や孫への住宅資金の援助ができますし、相続税対策にもなります。
亡くなる前3年以内の贈与はなかったものとして相続財産に加算する、贈与税の3年内加算の対象からも除外されています。
そのため、要件をしっかり理解して、適用を受け損ねるといったことのないように注意して下さい。
また、この制度の適用を受けるためには、贈与税が0円であったとしても期限内に贈与税の申告をすることが必ず必要です。
翌年3月15日を1日でも過ぎると、一切適用をしてもらえなくなってしまいます。くれぐれもご注意下さい。
(2020年8月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。