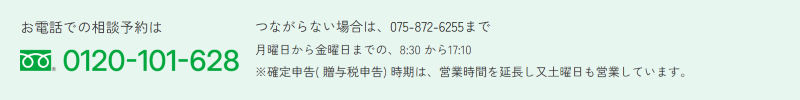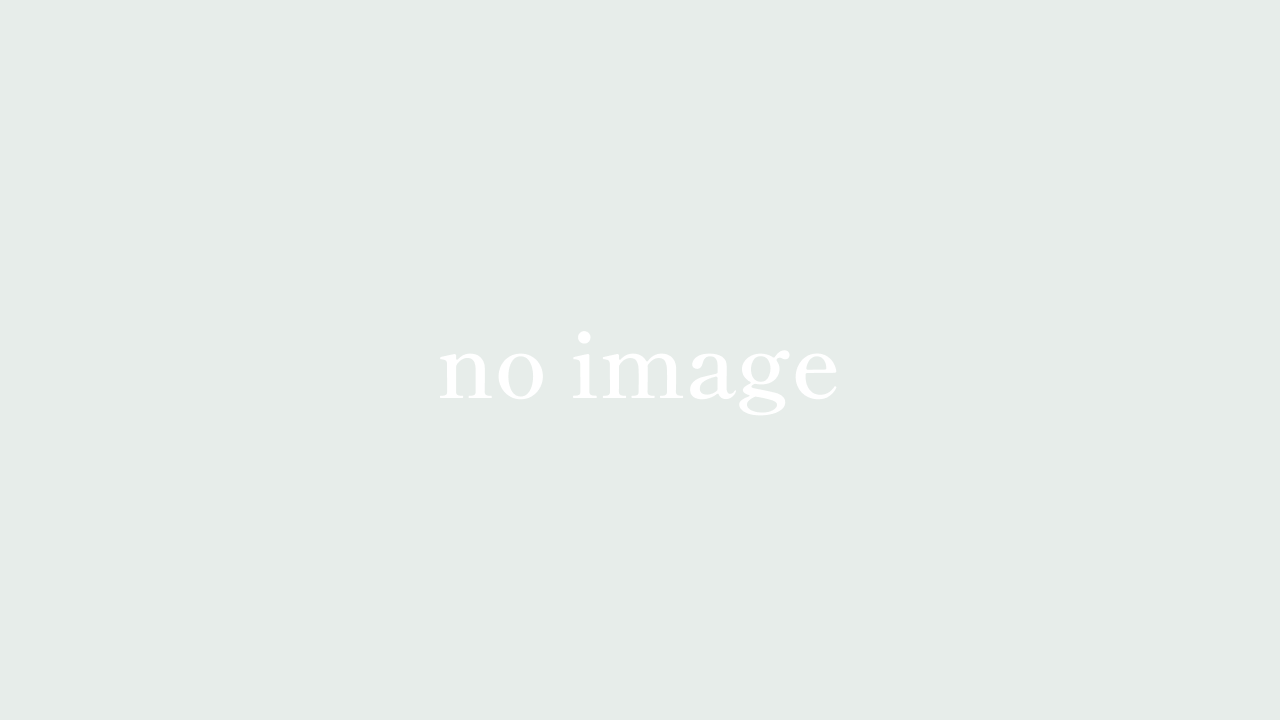小規模宅地等の減額で、税額が最も少なくなるという選択以外の選択ができるのか。
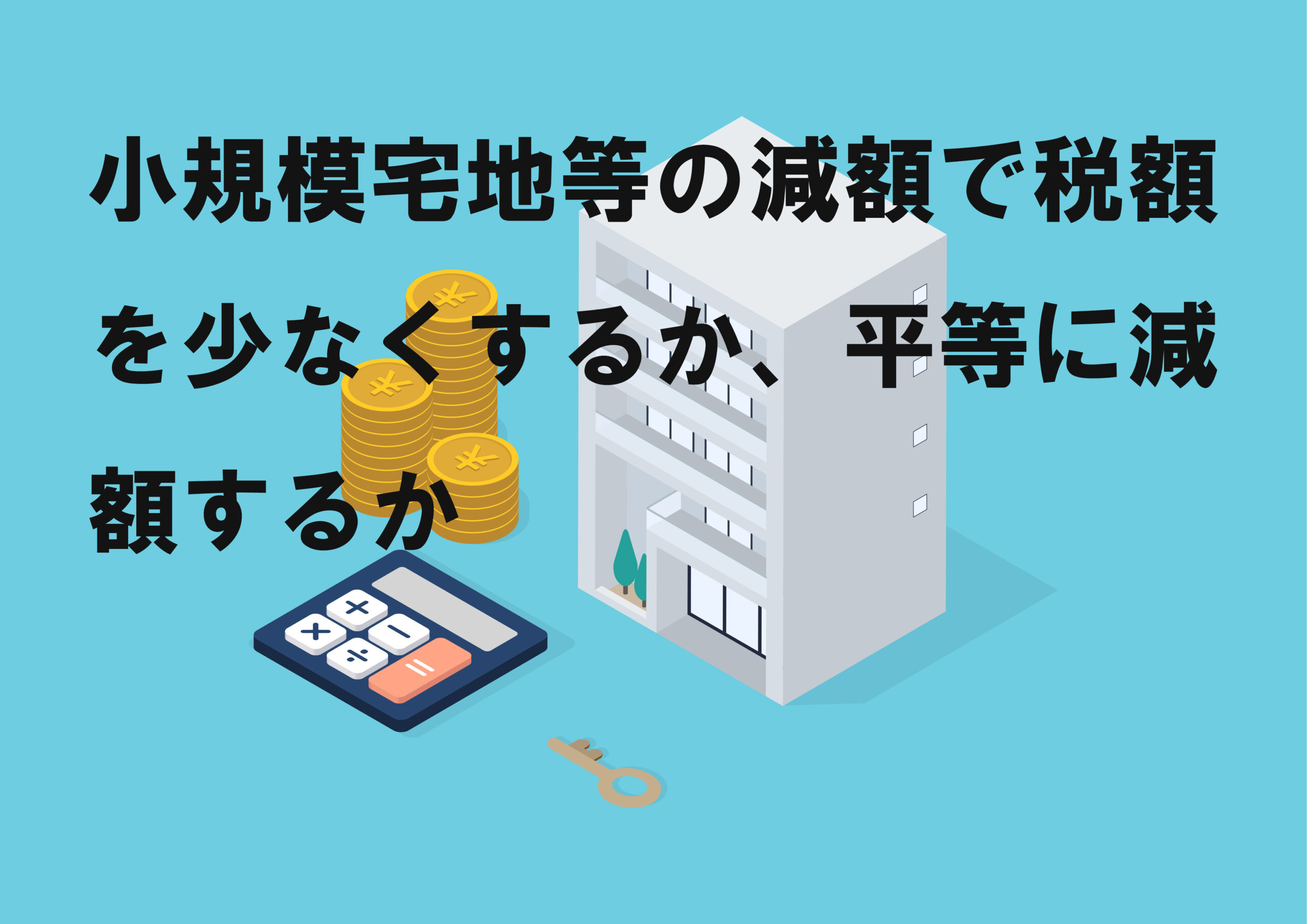
【小規模宅地等の減額で税額が最も少なくなるという選択以外の選択ができるのか。】
例えば、相続人甲取得A土地400㎡のうち100㎡と相続人乙取得B土地300㎡のうち100㎡を貸付事業用宅地等として選択して小規模宅地等の減額規定を適用するといったケースです。
小規模宅地の減額規定は相続税のなかでもなかなか複雑で難しい論点となります。ただし適用を受けることができると、大幅に相続税額を減額することができます。
今回はその小規模宅地等の減額規定でも応用編といえる内容です。小規模宅地等の減額規定の適用を受ける事ができる宅地(土地)が相続財産のなかに複数あり、相続人も配偶者を含めて複数いる場合は今回の論点が生じます。
小規模宅地等の減額規定は、その減額の対象となる宅地を取得した相続人等のすべての同意がなければ適用を受けることができず、相続税申告書にもその同意を署名する箇所が設けられています。
 |
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
(1)小規模宅地等の減額規定
小規模宅地等の減額規定とは、被相続人が亡くなられ相続人が相続などで取得した被相続人の相続財産のうち、相続開始の直前において被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定要件を満たすものについては、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税を計算するうえでの課税価格から、以下の割合を減額することができます。
| 宅地(土地)の種類 | 減額できる限度面積 | 減額できる割合 |
| ①特定居住用宅地等(被相続人が住んでいた土地) | 330㎡ | 80% |
| ②特定事業用宅地等(被相続人が事業をしていた土地) | 400㎡ | 80% |
| ③ 特定同族会社事業用宅地等(被相続人の同族会社のための土地) | 400㎡ | 80% |
| ④貸付事業用宅地等(被相続人が貸付事業をしていた土地) | 200㎡ | 50% |
・例1 夫が死亡し、相続人の妻が夫と住んでいた住居を相続する・・・その相続した住居のうち330㎡までが80%を差引いた金額で相続税評価される。(330㎡以内で1億円の土地の場合、2千万円で相続税評価)
・例2 父が死亡し、相続人の子が、父が生前に貸付事業を行っていた賃貸マンションを相続する・・・その相続したマンションの敷地のうち、200㎡までが50%を差引いた金額で相続税評価される。(200㎡以下で8000万円の土地である場合、4000万円で相続税評価)
ちなみに相続税の最低税率は10%、最高税率は55%です。
(2)小規模宅地等が複数ある場合
被相続人の財産に小規模宅地として減額できる土地が広大である場合や複数ある場合は、減額できる限度面積が以下のように定められています。
| 特例の適用を選択する宅地等 | 限度面積 |
| 特定居住用宅地等(①)、特定事業用宅地等(②)、特定同族会社事業用宅地等(③)
(貸付事業用宅地等がない場合) |
①≦330㎡
(②+③)≦400㎡ 両方を選択する場合は、合計730㎡ |
| 貸付事業用宅地等(④)およびそれ以外の宅地等(①、②または③) (貸付事業用宅地等がある場合) |
(②+③)×200/400+①×200/330 +(④)≦200㎡ |
貸付事業用宅地等を選択すると、他の宅地との組合せの合計面積が200㎡と最少となります。
(3)配偶者の税額軽減規定との関連
配偶者の税額軽減規定とは、被相続人の配偶者が相続等で取得した遺産額が、次の金額A.Bのどちらか多い金額までである場合には配偶者に相続税はかからないという制度です。(配偶者の相続後の生活の安定を保障するためなどが制度趣旨です)
A.1億6千万円 B.配偶者の法定相続分相当額
つまり上記AかBいずれか高い金額までは配偶者が相続等で取得した財産には相続税がかかりません。ここで、配偶者の税額軽減という規定と小規模宅地等の減額規定とのの兼ね合いが生じてきます。
小規模宅地等が複数ある場合、誰が取得した土地に減額規定を適用するかで納付税額の総額が変わってきます。
簡単に言うと、配偶者に小規模宅地等の減額規定を適用すると、配偶者の税額軽減規定と小規模宅地等の減額規定がダブる場合があり、その場合は配偶者以外の相続人が小規模宅地等の減額規定を適用した方が、相続税の納付税額の総額が少なくなります。(ちなみに税理士試験では、この論点を把握したうえで税額が最も安くなる計算方法を選択しなければなりません)
配偶者の財産取得分が法定相続分又は1億6千万円あたりで、この配偶者が小規模宅地等の減額規定を適用できたとしても、配偶者以外の相続人が小規模宅地等の減額を適用する方が有利になるケースが生じます。
ちなみに、手で計算すると結構大変ですが、税理士事務所が使っているような相続税申告ソフトであれば、比較的簡単に何通りかの小規模宅地等の減額規定適用パターン(例えば、配偶者のA土地に適用とか、相続人甲のB土地に適用、相続人乙のC土地に適用・・・など)
(4)貸付事業用宅地等を異なる相続人で100㎡ずつ適用
配偶者が小規模宅地等の減額規定を適用しないなら、誰が適用するかという問題が生じます。例えば相続人が配偶者と子2人(兄弟)であり、貸付事業用宅地等が2ヵ所以上ある場合です。兄弟でそれぞれ貸付事業用宅地等を1ヵ所ずつ取得した場合、どちらの子に小規模宅地等の減額を適用するかという選択が生じます。どちらかの子に適用すればその子の相続税納付税額は減少します。一方で適用がない子は納税額は変わりがありません。
平等にこだわるのであれば、どちらかの子に小規模宅地等の減額を適用するとして、兄弟で納税額と財産取得額を平等となるように計算して財産分けをするという方法もありますが、その計算は複雑です。
そこで、ひとつの方法があります。兄弟で平等に財産分けて貸付事業用宅地等もそれぞれ1ヵ所以上ずつ取得します。そして兄弟で100㎡ずつ小規模宅地等の減額を適用するという方法です。
この方法だと財産を平等に兄弟で分け、減税規程も平等に適用するというシンプルで分かりやすく、減税額が平等であると感覚的に実感できる方法です。ただし、納付すべき相続税額の合計額が最少とならない可能性もあります。
相続税申告のご相談は税理士法人吉本事務所へ

相続税申告のご相談は、税理士法人吉本事務所へお任せください!
当事務所には100件以上の申告実績を誇る相続専門の税理士が、お客様に寄り添いながら申告のサポートを一貫して行います。
また、相続税がかからない場合の相続手続きにも対応しております。
以下のようなお悩みがございましたら、些細なことでもお答えいたしますので、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。
| ・相続税はいくらかかるのか ・相続税の負担を軽減するにはどうすればよいか ・どのように遺産を分ければ負担を軽減できるか ・相続の手続きはどのように進めればよいか ・申告まで安心して任せたい ・相続税を現金で納付するのが難しい など |