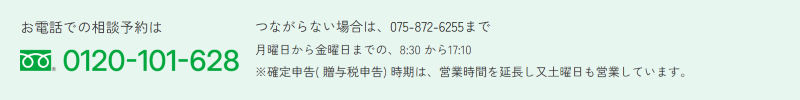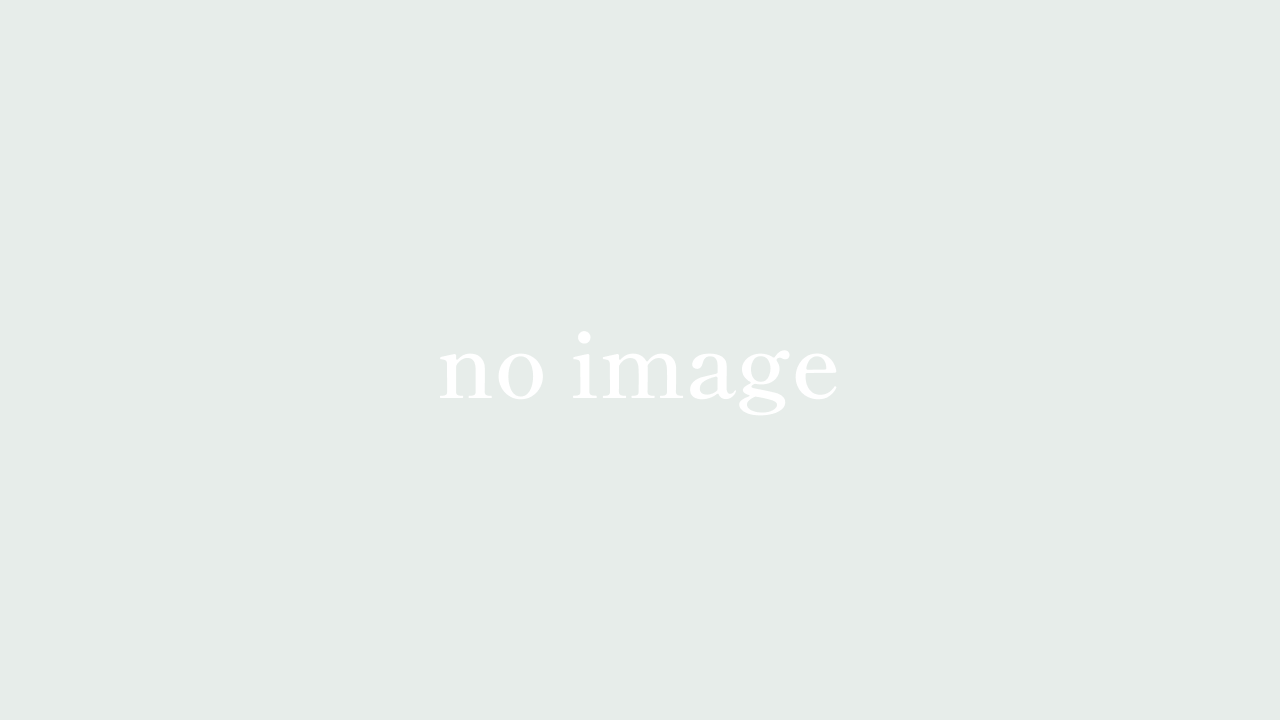【最新】遺産総額5,000万円の相続税はいくら?ケース別の早見表や計算方法を税理士がわかりやすく解説
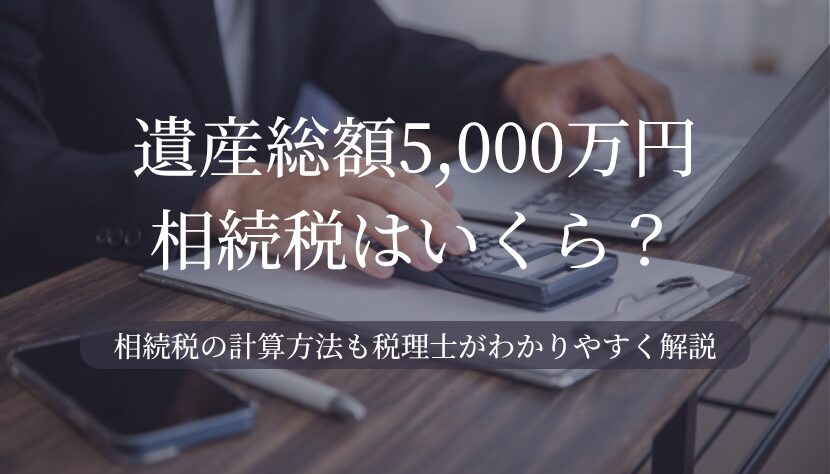
遺産総額5,000万円の相続税がいくらか知りたい方は、相続税の早見表でおおよその相続税額を確認してみましょう。
本記事では、以下のケースに分けて早見表を用意しました。
・配偶者と子どもが相続人のケース
・配偶者と父母が相続人のケース
・配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース
・配偶者のみが相続人のケース
・子どものみが相続人のケース
・父母のみが相続人のケース
・兄弟姉妹のみが相続人のケース
また、相続税の計算方法や相続税を減らせる主な控除・特例もわかりやすく解説します。
 |
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
遺産総額5,000万円の相続税はいくら?
遺産総額5,000万円の相続税がいくらかは、誰がどの割合で遺産を相続するかなどによって変わります。
遺産を相続する人は「法定相続人」として民法で定められているため、相続税の早見表を確認する前に誰が相続人かを把握しておきましょう。
| 必ず相続人 | 被相続人の配偶者 |
| 第1順位 | 被相続人の子ども (子どもが死亡している場合は孫) |
| 第2順位 | 被相続人の父母 (父母が死亡している場合は祖父母) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 (兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪) |
死亡した人に配偶者がいる場合は必ず配偶者が相続人になり、配偶者以外の人は順位が高い人のみが配偶者と相続人になります。
遺産総額5,000万円の相続税の早見表【ケース別】
ここからは、遺産総額5,000万円の相続税の早見表を以下のケースに分けて解説します。
・配偶者と子どもが相続人のケース
・配偶者と父母が相続人のケース
・配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース
・配偶者のみが相続人のケース
・子どものみが相続人のケース
・父母のみが相続人のケース
・兄弟姉妹のみが相続人のケース
前提として、法定相続分(民法で定められた相続の割合)で相続し、配偶者には配偶者の税額軽減を適用した場合のおおよその相続税額です。
実際に遺産を相続する人や相続の割合は家庭によって異なり、必ずしも法定相続分の通りに相続するとは限らないので、相続税額を正確に知りたい方は税理士に相談することをおすすめします。
配偶者+子どもが相続人のケース
遺産総額5,000万円で、配偶者と子どもが相続人のケースでは、配偶者と子ども1人の場合で相続税は40万円、配偶者と子ども2人の場合で10万円になります。
配偶者は配偶者の税額軽減により相続税が0円になるため、子どもが負担する相続税額です。
子どもが2人の場合は、1人あたり5万円(10万円÷2)の相続税を納めることになります。
なお、子どもが3人以上なら遺産総額の5,000万円より基礎控除額が上回るため、相続税はかかりません。
▼配偶者+子どもが相続人の場合の相続税早見表
| 遺産総額 | 配偶者+子ども1人 | 配偶者+子ども2人 | 配偶者+子ども3人 | 配偶者+子ども4人 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 1億 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合
配偶者の税額軽減は、以下の記事で詳しく解説しています。
配偶者+父母が相続人のケース
遺産総額が5,000万円で、配偶者と父母が相続人のケースでは、配偶者と父母1人(どちらかが他界)の場合で相続税は27万円、配偶者と父母2人の場合で7万円になります。
配偶者は配偶者の税額軽減により相続税が0円になるため、父母が負担する相続税額です。
▼配偶者+父母が相続人の場合の相続税早見表
| 遺産総額 | 配偶者+父母1人 | 配偶者+父母2人 |
| 5,000万円 | 27万円 | 7万円 |
| 1億 | 271万円 | 222万円 |
| 1億5,000万円 | 660万円 | 583万円 |
※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合
配偶者+兄弟姉妹が相続人のケース
遺産総額5,000万円で、配偶者と兄弟姉妹が相続人のケースでは、配偶者と兄弟姉妹1人の場合で相続税は29万円、配偶者と兄弟姉妹2人の場合で7万円になります。
配偶者は配偶者の税額軽減により相続税が0円になるため、兄弟姉妹が負担する相続税額です。
兄弟姉妹が3人以上なら遺産総額の5,000万円より基礎控除額が上回るため、相続税はかかりません。
▼配偶者+兄弟姉妹が相続人の場合の相続税早見表
| 遺産総額 | 配偶者+兄弟姉妹1人 | 配偶者+兄弟姉妹2人 | 配偶者+兄弟姉妹3人 | 配偶者+兄弟姉妹4人 |
| 5,000万円 | 29万円 | 7万円 | 0円 | 0円 |
| 1億 | 301万円 | 256万円 | 218万円 | 180万円 |
| 1億5,000万円 | 750万円 | 676万円 | 612万円 | 558万円 |
※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合
※兄弟姉妹は2割加算
配偶者のみが相続人のケース
遺産総額5,000万円で、配偶者のみが相続人のケースでは、配偶者の税額軽減を適用すれば相続税は0円です。
死亡した人の配偶者が遺産を相続するときは、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
相続人が配偶者のみの場合は法定相続分が100%になるため、いくら相続しても相続税は0円になります。
ただし、配偶者の税額軽減を適用するには、相続税が0円でも申告が必要です。
子どものみが相続人のケース
遺産総額が5,000万円で、子どものみが相続人のケースでは、子ども1人の場合で相続税は160万円、2人の場合で80万円、3人の場合で20万円です。
子どもが4人以上なら遺産総額の5,000万円より基礎控除額が上回るため、相続税はかかりません。
なお、配偶者がいる場合と比べると、基礎控除額が減るほか、配偶者の税額軽減が使えないことから相続税が高くなります。
▼子どものみが相続人の場合の相続税早見表
| 遺産総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
父母のみが相続人のケース
遺産総額が5,000万円で、父母のみが相続人のケースでは、父母1人(どちらかが他界)の場合で相続税は160万円、父母2人の場合で80万円です。
配偶者がいる場合と比べると、基礎控除額が減るほか、配偶者の税額軽減が使えないことから相続税が高くなります。
▼父母のみが相続人の場合の相続税早見表
| 遺産総額 | 父母1人 | 父母2人 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 |
| 1億 | 1,220万円 | 770万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 |
兄弟姉妹のみが相続人のケース
遺産総額が5,000万円で、兄弟姉妹のみが相続人のケースでは、兄弟姉妹1人の場合で相続税は192万円、2人の場合で96万円、3人の場合で23万円です。
兄弟姉妹が4人以上なら遺産総額の5,000万円より基礎控除額が上回るため、相続税はかかりません。
▼兄弟姉妹のみが相続人の場合の相続税早見表
| 遺産総額 | 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 | 兄弟姉妹4人 |
| 5,000万円 | 192万円 | 96万円 | 23万円 | 0円 |
| 1億 | 1,464万円 | 924万円 | 756万円 | 588万円 |
| 1億5,000万円 | 3,432万円 | 2,208万円 | 1,728万円 | 1,488万円 |
※兄弟姉妹は2割加算
遺産総額5,000万円の相続税を確認するときの注意点
遺産総額5,000万円にいくら相続税がかかるかを確認するときは、以下2点に注意しましょう。
1.遺産総額は本当に5,000万円か
2.相続税の基礎控除額はいくらか
順に解説します。
1.遺産総額は本当に5,000万円か
相続財産は、死亡した人から相続した現金、預貯金、不動産だけではありません。
以下のようにプラスの財産とマイナスの財産に分かれ、プラスの財産の合計額からマイナスの財産の合計額を差し引いて残った金額が遺産総額です。
| プラスの財産 現金、預貯金、土地、建物、借地権、株式、公社債、貴金属、自動車、骨董品、美術品、生命保険金(非課税枠を超える金額)、死亡退職金(非課税枠を超える金額)、会員権、著作権、特許権など |
| マイナスの財産 葬式費用、借金、未払金、ローン残債、保証人・連帯保証人の地位、未納の税金、損害賠償責任など |
なお、財産の種類ごとに相続税評価額(相続税を計算するための財産の価額)を計算する必要があり、ここで計算を誤ってしまうと相続税額が増減します。
遺産総額は本当に5,000万円かを再度確認し、実際に相続するときは税理士に相談しましょう。
2.相続税の基礎控除額はいくらか
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは、遺産総額から差し引ける控除のことです。
遺産総額が5,000万円の場合、基礎控除額が5,000万円を超えれば相続税はかかりません。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
遺産総額が5,000万円であれば、法定相続人が4人以上のときは相続税がかからないことになります。
反対に、法定相続人が3人以下のときは相続税がかかります。
相続税の基礎控除額や法定相続人の考え方は、以下の記事で詳しく解説しています。
遺産総額5,000万円の相続税を計算する方法
ここからは、以下のケースを想定して遺産総額5,000万円の相続税の計算方法を解説します。
| 遺産総額 | 5,000万円 |
| 相続人 | 配偶者+子ども2人=計3人 |
1.基礎控除額を計算する
まずは、基礎控除額から計算しましょう。
| 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円になります。
| 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
なお、先述の通り基礎控除額が5,000万円を超える方は相続税がかからないため、これ以上計算する必要はありません。
2.課税遺産総額を計算する
遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算しましょう。
| 課税遺産総額=遺産総額-基礎控除額 |
遺産総額が5,000万円で、基礎控除額が4,800万円の場合、課税遺産総額は200万円になります。
| 5,000万円-4,800万円=200万円 |
3.相続税の総額を計算する
各相続人の概算の相続税額と相続税の総額を計算しましょう。
各相続人の相続税額の合計額が相続税の総額になります。
| 各相続人の相続税額=課税遺産総額×法定相続分×税率-控除額 |
※法定相続分、税率、控除額は後述の表を確認する
配偶者と子ども1人あたりの概算の相続税額は、以下の通りです。
| 配偶者 | 200万円×50%×10%=10万円 |
| 子ども1人あたり | 200万円×25%×10%=5万円 |
合計すると、相続税の総額は20万円になります。
| 10万円+5万円+5万円=20万円 |
▼法定相続分の割合
| 配偶者のみが相続人のケース | 配偶者1 |
| 配偶者と子どもが相続人のケース | 配偶者2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
| 配偶者と父母または祖父母が相続人のケース | 配偶者3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース | 配偶者4分の3 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
▼相続税の税率・控除額
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4.各相続人の納税額を計算する
法定相続分ではなく、実際に相続する割合を反映して各相続人の納税額を計算しましょう。
| 各相続人の納税額=相続税の総額×〇%(実際に相続する割合) |
実際にも法定相続分で相続したとすると、配偶者と子ども1人あたりの納税額は以下の通りです。
| 配偶者 | 20万円×50%=10万円 |
| 子ども1人あたり | 20万円×25%=5万円 |
なお、配偶者は配偶者の税額軽減を適用できるため、配偶者の納税額は10万円から0円になります。
相続税を減らせる主な控除・特例
相続税には基礎控除の他にも以下のような控除や特例があり、使うことができれば相続税を減らせます。
1.配偶者の税額軽減
2.未成年者控除
3.障害者控除
4.贈与税額控除
5.相次相続控除
6.外国税額控除
7.小規模宅地等の特例
8.農地等の納税猶予の特例
ただし、それぞれ要件を満たす必要があるため、相続税がかかる場合は税理士に相談しましょう。
1.配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者は、相続した遺産が1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない制度です。
簡単に言い換えると、被相続人の配偶者は最低1億6,000万円の遺産を相続しても相続税はかかりません。
ただし、この制度を使うときは相続税の申告が必要です。
注意点として、子どもがいる場合は配偶者から子どもへの相続(二次相続)を考慮して遺産を分けなければ、二次相続で相続税が高くなる可能性があります。
国税庁:配偶者の税額の軽減
2.未成年者控除
未成年の法定相続人は、相続税額から以下の金額を差し引ける制度です。
| 未成年者控除の控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円 |
法定相続人が10歳1か月とすると、1年に満たない期間は切り捨て10歳として計算します。
| (18歳-10歳)×10万円=80万円 |
国税庁:未成年者の税額控除
3.障害者控除
障害者に該当する85歳未満の法定相続人は、相続税額から以下の金額を差し引ける制度です。
| 障害者控除の控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円※ ※特定障害者に該当する場合は20万円 |
法定相続人が29歳10か月とすると、1年に満たない期間は切り捨て29歳として計算します。
| (85歳-29歳)×10万円=560万円※ ※特定障害者に該当する場合は1,120万円 |
国税庁:障害者の税額控除
4.贈与税額控除
被相続人から生前に財産の贈与を受けて贈与税を納めていたときは、相続税額から贈与税相当額を差し引ける制度です。
5.相次相続控除
今回の相続が発生する前の10年以内に、被相続人が財産を相続して相続税を納めていたときは、相続税額から一定の金額を差し引ける制度です。
国税庁:相次相続控除
6.外国税額控除
国外の財産を相続して相続税に相当する税金がかかるときは、相続税額から以下の金額のいずれか少ない金額を差し引ける制度です。
| ・国外で課された税額 ・相続税額×(国外にある相続財産の合計額/相続人の相続財産の合計額) |
7.小規模宅地等の特例
事業用または居住用として使われていた土地を相続するときは、一定の面積の評価額を最高80%まで減額できる制度です。
土地の用途、面積、相続する人など細かい要件を満たさなければなりませんが、相続税を大幅に減らせる可能性があります。
この制度を使うときは、相続税の申告が必要です。
国税庁:小規模宅地等の特例
8.農地等の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人から農地を相続して農業を継続するときは、一定の相続税額の納税が猶予される制度です。
この特例を使うときは、相続税の申告が必要です。
相続税がかかる場合は10か月以内に申告を
遺産総額が5,000万円の場合、相続税がかかる方もいれば、かからない方もいます。
結果として相続税がかかる方は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に申告が必要です。
また、先述の特例や控除の中には相続税が0円でも申告が必要なものもあります。
相続財産を見落としていたり相続税評価額の計算が誤っていたりしても、正しい申告ができなくなるため、実際に相続するときは税の専門家である税理士を頼りましょう。
相続税に関するご不安は税理士法人吉本事務所へ

・相続税がかかるかわからない
・相続税がいくらかかるか知りたい
・相続税を減らすにはどうしたらよいか
・どのような特例や控除が使えるか
などのお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください!
当事務所には相続専門の税理士が在籍しており、相続税の計算、申告、相続税対策など全般のご相談・ご依頼をお受けしています。
おおよその相続税額は相続税の早見表で把握していただけますが、遺産の分け方や使える特例の種類などでも変わります。
私どもは長年の経験と知識を活かした相続税対策を強みとし、お客様にとってベストな選択をご提案いたしますのでどうぞご安心ください。
また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、相続の手続きやお悩みにも幅広く対応可能です。
相続税のお見積りは無料でお受けしていますので、些細なことでもお気軽に税理士法人吉本事務所までご相談ください。
当事務所のホームページはこちらから
無料お見積り・お問い合わせはこちらから
まとめ
遺産総額5,000万円の相続税がいくらかは、おおよその相続税額であれば早見表でわかります。
遺産総額5,000万円の場合、早見表の通り相続税がかかる方もいれば、かからない方もいます。
相続税は遺産総額に対して一律でかかるものではないため、あくまで目安と考え、厳密な計算は税理士に依頼しましょう。