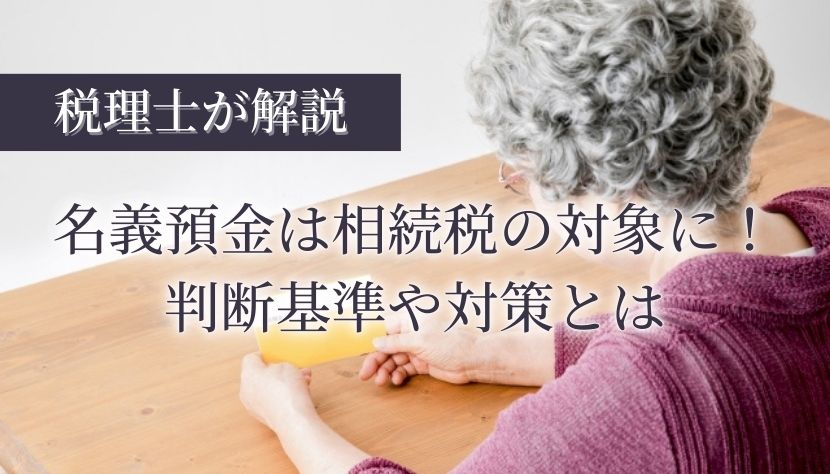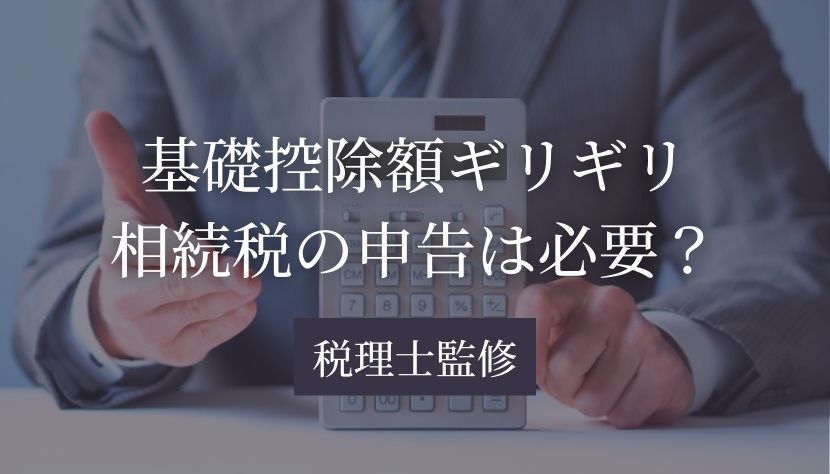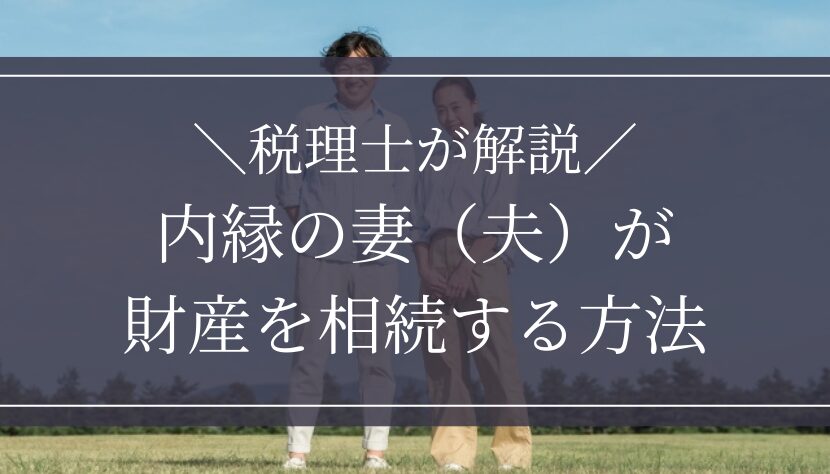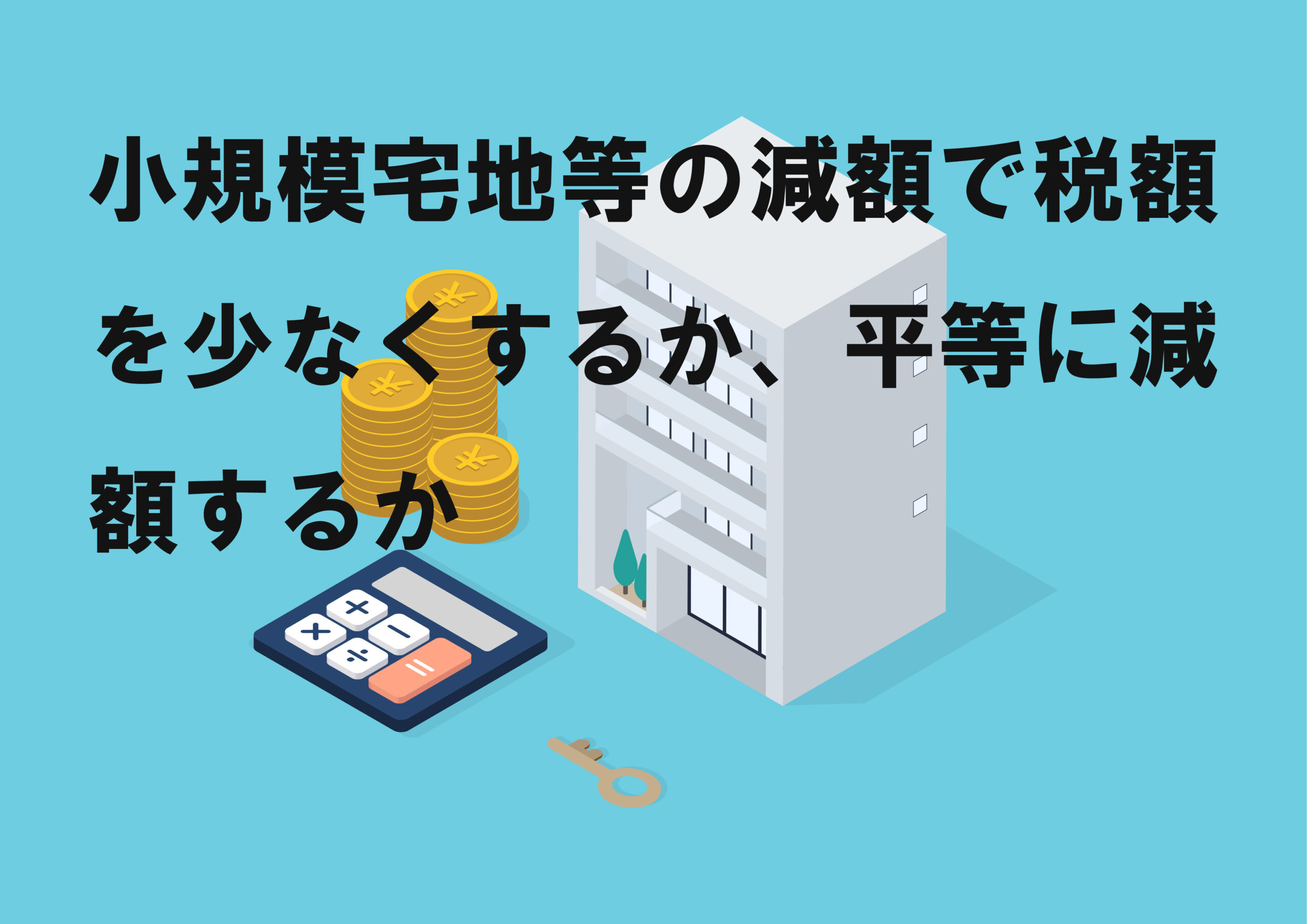Point
遺族年金等の
受取手続きについて
当事務所には社会保険労務士が在籍しており、遺族年金に関する各種手続きのサポートも行っております。
遺族年金の申請は必要書類が多く、制度も複雑でわかりにくいため、ご遺族の方にとっては精神的にも大きな負担になりがちです。
特に、相続と同時期に進める必要がある場合、何から手をつけてよいかわからず、お困りになる方も少なくありません。
当事務所では、社会保険の制度や年金の仕組みに精通した社会保険労務士が、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金などの受給要件や申請手続きについて丁寧にご案内いたします。また、必要に応じて申請書類の作成支援や提出代行も承っております。

各種遺族年金の受給
01遺族基礎年金(国民年金)
1. 支給要件
- ・被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなられたとき
- ・亡くなられた方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
- ※ただし、亡くなられた日が令和18年3月末日までの場合は、亡くなられた方が65歳未満であれば、亡くなられた日が含まれる月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2. 対象者
亡くなられた方によって生計を維持されていた、子のある配偶者、子
※子とは次の者に限ります
- ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
3. 請求先
最寄の年金事務所等
02寡婦年金(国民年金)
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたとき、婚姻関係及び生計維持関係が10年以上継続してあった妻が60歳から65歳になるまで、一定額が支給されます。
ただし、亡くなられた夫が老齢基礎年金の支給を受けてない場合に限ります。
03死亡一時金(国民年金)
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が老齢・障害基礎年金等を受けずに亡くなられたとき、生計を同じくしていたご遺族に支給されます。
04遺族厚生年金
(厚生年金保険)
1. 支給要件
A
- ・被保険者が亡くなられたとき
- ・被保険者期間中の傷病により初診の日から5年以内に亡くなられたとき
- ・亡くなられた方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること
※ただし、亡くなられた日が令和18年3月末日までの場合は、亡くなられた方が65歳未満であれば、亡くなられた日が含まれる月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
B
老齢厚生年金の資格期間を満たした者が亡くなられたとき
C
1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなられたとき
2. 対象者
第1順位
- 子のある配偶者
- 子(※注)
- 子のない配偶者(55歳以上)
第2順位
父母(55歳以上)
第3順位
孫(※注)
第4順位
祖父母(55歳以上)
また、子のある妻、子(※注)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
(※注)18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者
3. 加算額
以下に掲げるような一定の要件を満たす場合は、一定の金額が加算されます。
- ・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- ・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
- ・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき
- ・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2.の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります。)
4. 請求先
最寄の年金事務所
05遺族共済年金(各種共済)
公務員などが加入する共済組合やJA共済、全労済、都道府県民共済などの各種共済組合から支給される遺族年金です。
共済の種類により、上記の遺族基礎年金のように、一定の要件を満たしているご遺族に一定の計算方法に基づき支給されます。
請求先は所属する共済組合等となります。
06遺族補償給付(労災保険)
1. 内容
労災保険の遺族補償給付は、仕事中や通勤により亡くなられた労働者のご遺族に支給されます。
遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金があり、労働者の亡くなられた当時の生計維持関係や亡くなられた労働者との続柄、ご遺族の年齢などによって、いずれかになります。
A
遺族補償年金(遺族年金)
遺族補償年金を受けることができるご遺族は、労働者の亡くなられた当時の収入によって生計を維持していた配偶者や子供、親、孫、祖父母、兄弟姉妹などです。
ただし、妻以外のご遺族の場合、一定の年齢または一定の障害の状態にあることが必要です。
なお、遺族補償年金の受給権者が希望すれば、1回に限り、一定額までまとめて前払いを受けられます。(遺族補償年金前払一時金。亡くなられた後は、一時的にさまざまな費用が生じることが多いからです。)
B
遺族補償一時金(遺族一時金)
遺族補償一時金は、労働者の亡くなられた当時、上記の遺族補償年金の受給資格者がないときに定められた順位に従い、最先順位の方に対して支給されます。
亡くなられた労働者の収入によって生計を維持していたご遺族がいない場合や、生計を維持していたご遺族はいるものの年齢条件を満たさないなどの理由によります。
2. 申請書の提出先
生前にお勤めであった事業所の所轄の労働基準監督署
3. 申請期限
労働者が亡くなられた後、速やかに。
労働者が亡くなってから5年を経過すると、時効によって請求する権利が消滅します。
相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。