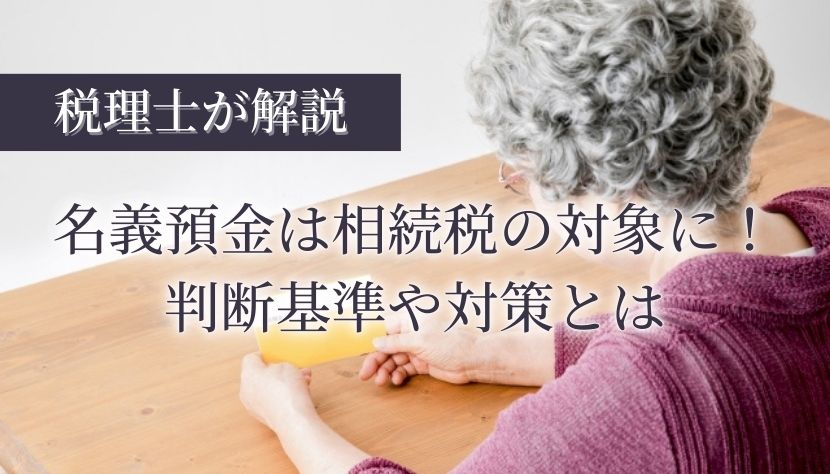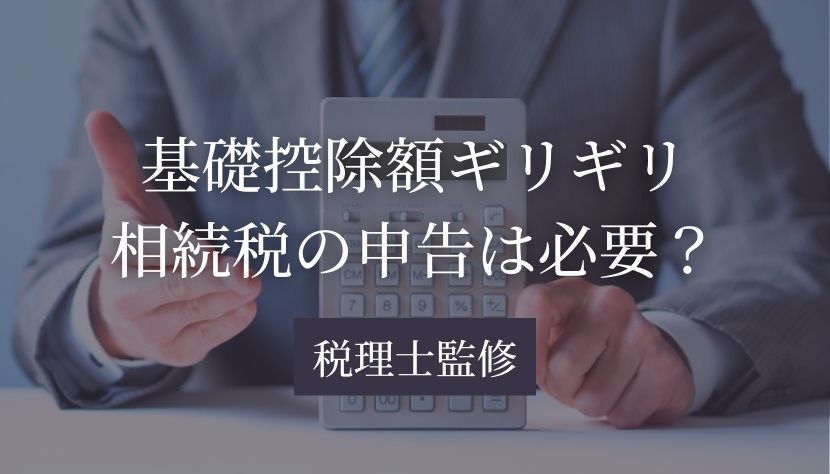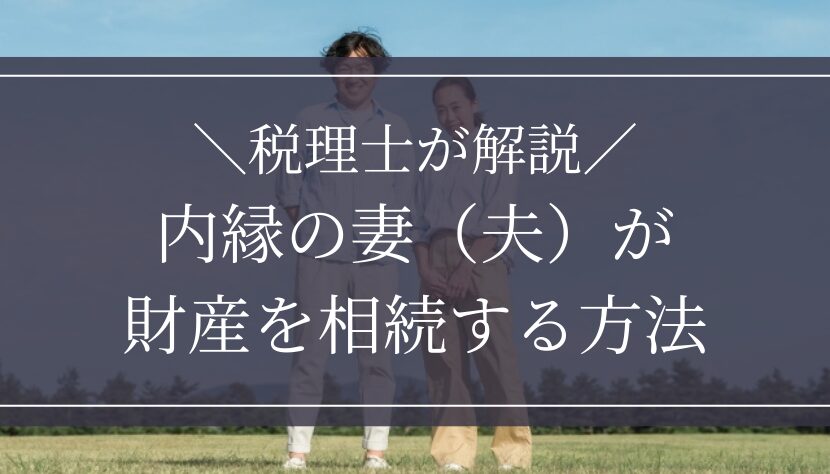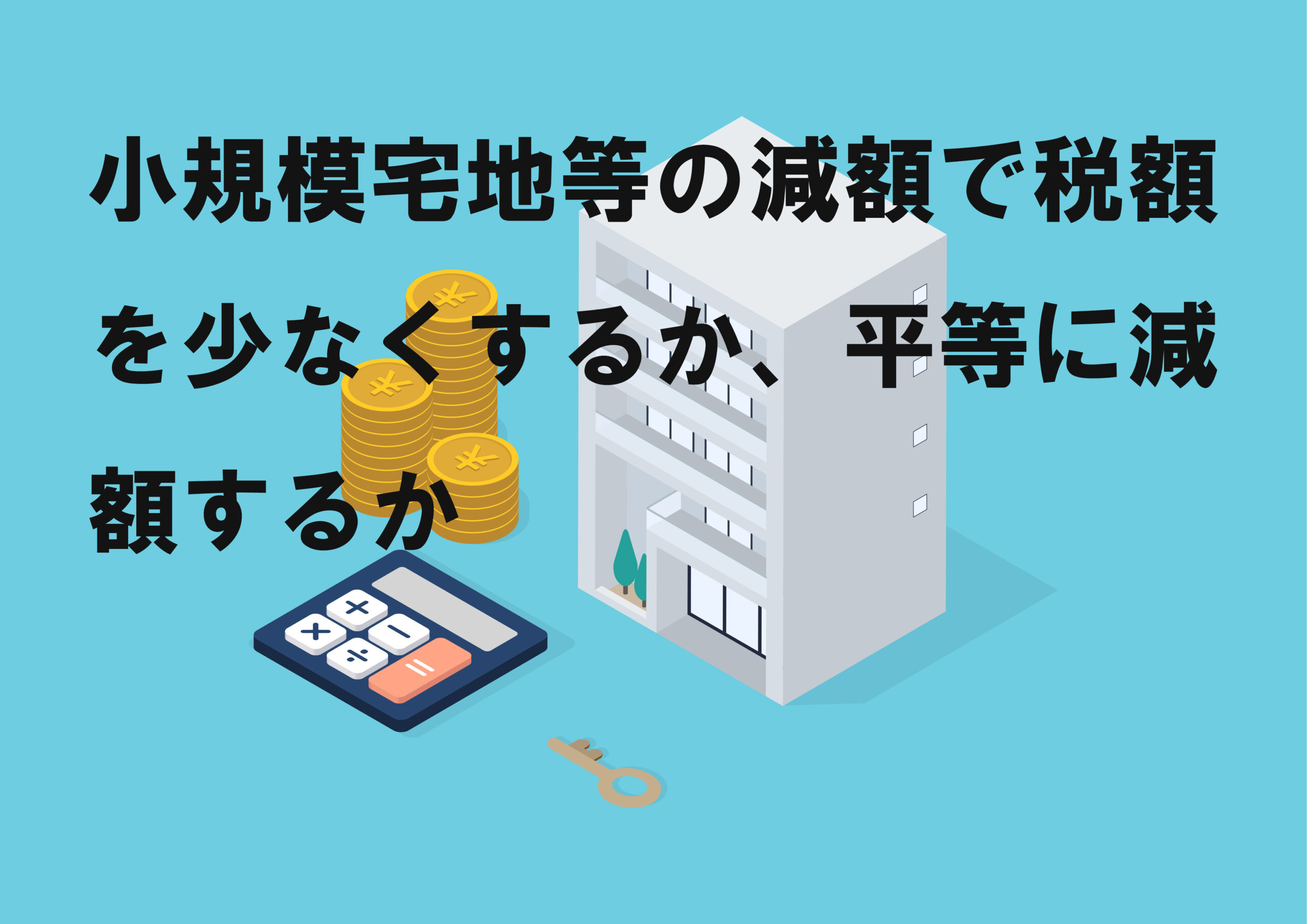Point
税務調査とは?
税務調査とは、納税者が提出した申告書が税法に準拠して正しく作成されているかどうかを国税局や税務署が実地で行う調査のことです。
税務調査というと、マル査を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、マル査は悪質な脱税者に対する強制捜査で、通常は納税者の同意を基とした任意捜査となります。
とはいえ「任意調査なら黙秘権が行使できるか?」というと、できません。
税務調査では調査受任義務が課せられているので、税務署員の質問に答えなかったり帳簿を見せなかったりすると罰則を受けます。

税務調査は何のために行われる?
税務調査は、租税負担を公平にすることを目的に行われます。ある納税者は税法のルール通りに申告しているのに、ある納税者はルール通りに申告していないとなると、税負担の公平を欠き、多くの納税者の納税意識を減退させてしまうためです。また、相続税・贈与税は納税者が自ら申告し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。この制度を円滑に運営していくために、申告が適正かどうかを確かめる目的もあります。
実際どのくらい調査がある?
令和6年12月に国税庁が発表したデータは、以下の通りです。
| 事務年度 | 令和4事務年度 | 令和5事務年度 |
|---|---|---|
| 実地調査件数 | 8,196件 | 8,556件 |
| 申告漏れ等の非違件数 | 7,036件 | 7,200件 |
| 非違割合 | 85.8% | 84.2% |
また、実地調査件数と申告漏れ等の非違件数から、税務調査が行われると約85%と非常に高い割合で追徴課税が課されていることがわかります。
どんな人に税務調査がくる?
遺産総額がおおむね3億円以上ある場合、税務調査が行われる確率は非常に高いでしょう。
その他にも、申告書上で大きな間違いがあったり、申告漏れや不明な部分があったりすれば、課税価格にかかわらず調査の対象になる可能性が高くなります。
また、申告義務があるのに申告しなかった人のところへも調査は入ります。
というのは、税務署は銀行や市区町村、保険会社などから、預金や固定資産、生命保険などの金額の報告を受けるので、相続税の申告をしなくても財産を把握しているからです。

相続税の税務調査のポイント
相続税の税務調査で問題となるポイントは、主に以下のような生前贈与に関することです。
(1)名義預金
家族名義であっても実質の所有者は誰かを問われます。
名義を変えているだけで贈与の実態が伴っていなければ、何年前の贈与でも相続税の対象になります。
(2)生命保険
契約者は妻であっても実質的に被相続人が保険料を支払っていれば、相続税の対象になります。
(3)株式等
家族の収入に見合わない家族名義の投資信託や株式等がある場合、購入資金の出所や実質的な所有者を問われます。
(4)不動産
家族の不動産購入時に資産の贈与がなかったか、購入時の年齢が若く低収入であるのに高額な不動産でないか、自用地、貸地、貸家、貸家建付地などの評価が適正であるかなどに注意が必要です。
税務調査の流れ
01相続税・贈与税の申告書の税理士欄に税理士の署名押印があれば税理士へ、署名押印がなければ納税者へ、調査官から調査がある旨の連絡がきます。
税理士に連絡があった場合は、納税者の都合のよい日を確認したうえで調査官と調査の日を決定します。
直接、納税者に連絡があり、指定された日時の都合が悪い場合は変更を申し出ても差し障りありません。なお、税理士の立ち会いを求める場合は日程の調整が必要になるので、調査の日時には即答せず、税理士と相談したうえで後日回答しましょう。
(事前連絡のない調査は相続税・贈与税ではほぼありませんが、もしあれば慌てずに税理士と連絡を取りましょう。)

02税務調査の期間は、1日で終了することもあれば数か月かかることもあります。
調査官の質問には、はっきりと正確に答えるのが鉄則です。
また、あらかじめ必要な書類などを準備しておけば、調査がスムーズに進み好印象でしょう。当事務所に依頼していただければ、書類確認や質問事項の確認など、事前準備のご指導をさせていただきます。
03税務調査で何も問題がなければ、申告是認で調査は終わり、追徴課税も課されません。
調査官が申告に誤りがあると指摘した場合、指摘事項を検討します。
税額が不足しており納税者が納得したときは、修正申告をして不足分の税金を支払います。(加算税と延滞税がかかります。)
納得できないときは、税理士と調査官が話し合って税法に適合しているかどうかを検討し、調査官が「問題なし」と認めることもあれば「やはり問題あり」と判断されることもあります。
調査官とのやり取りの後、納税者が納得すれば修正申告をして不足分の税金を支払いますが、納得せずに申告書を提出しなかった場合は税務署長が決定処分を行って税額を確定します。
(決定処分にも納得できない場合、納税者は不服申し立てをすることができます。)
相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。