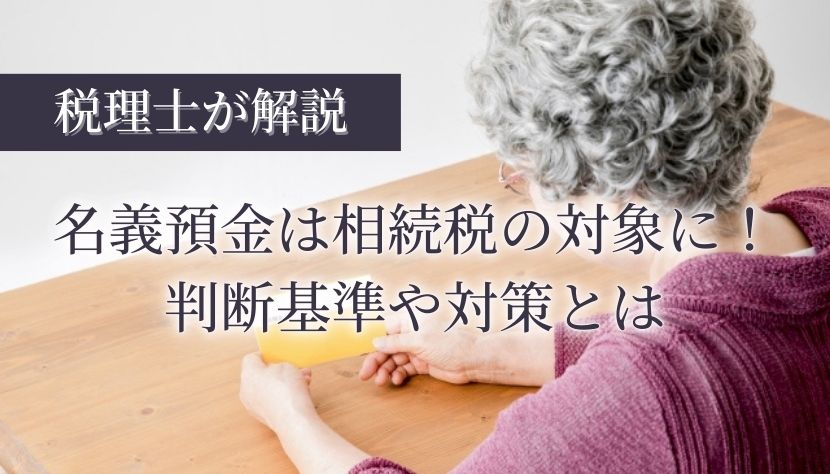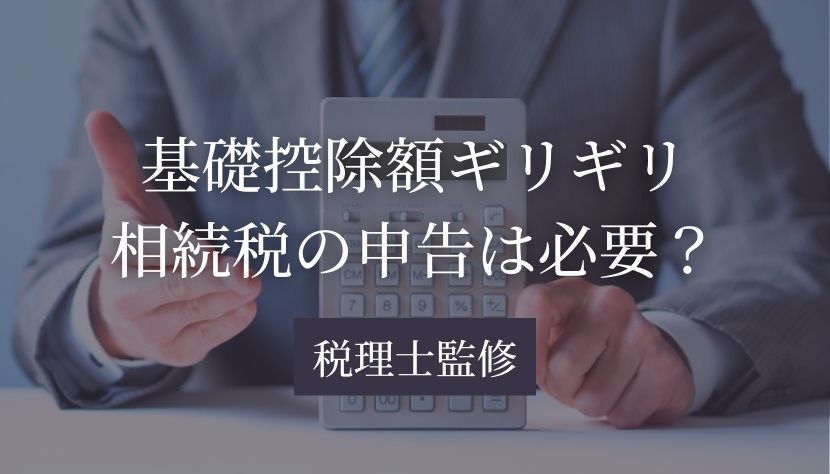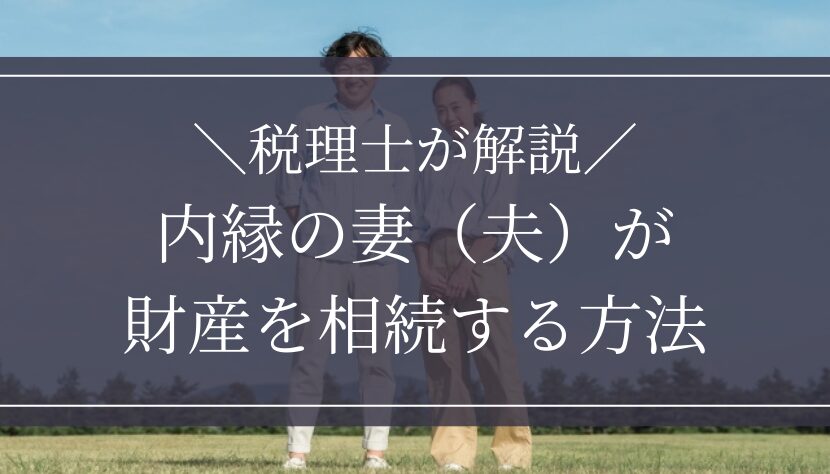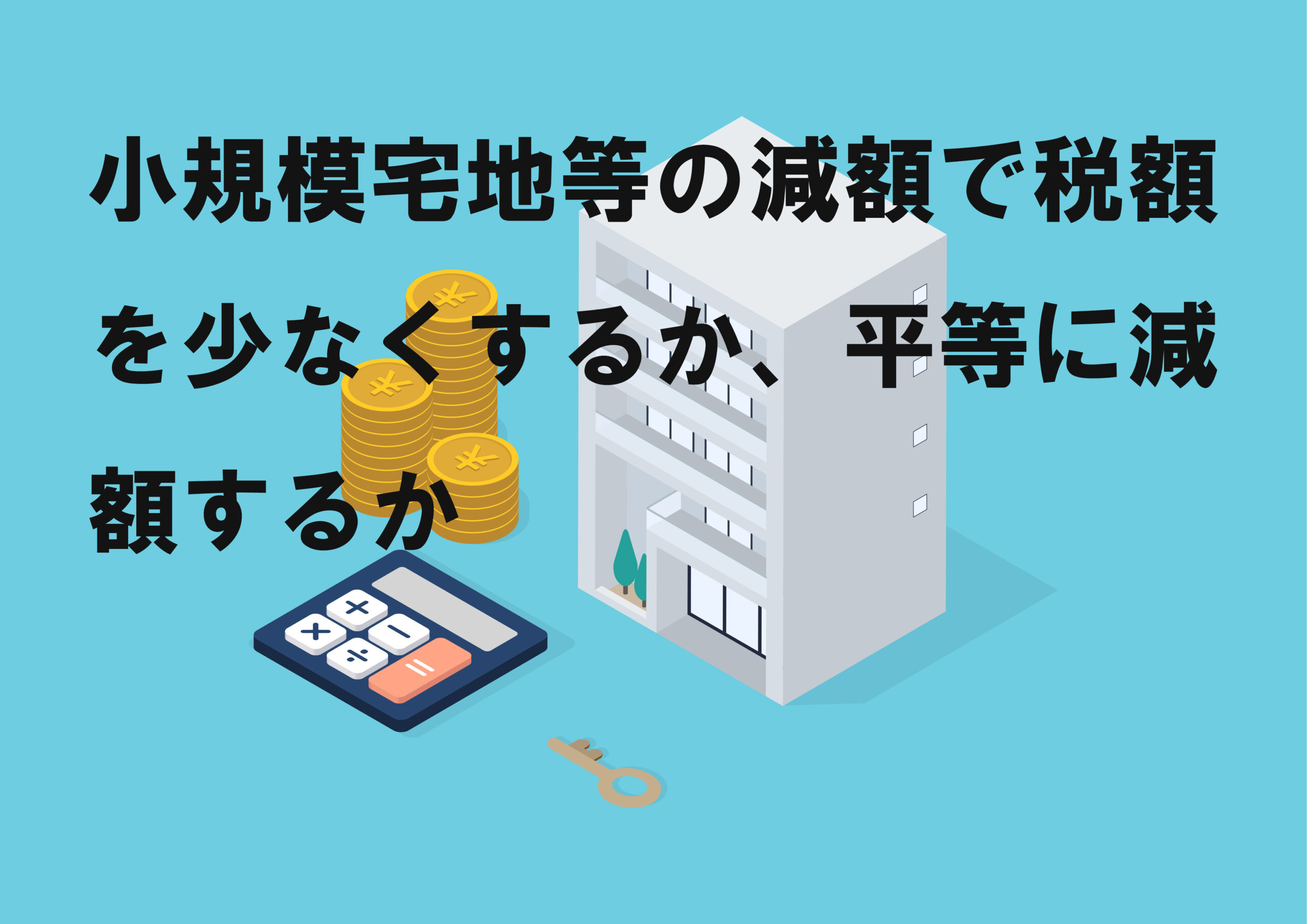遺言書を作成するメリット
公正証書遺言がある場合、その内容に基づいてスムーズに相続手続きを進めることができます。たとえば、不動産の名義変更や銀行口座の解約なども、遺言書に従って簡単に行うことが可能です。
通常必要とされる他の相続人の署名や押印も不要で、遺産分割について話し合う必要もありません。そのため、遺産分割協議書を作成する手間も省け、相続をめぐるトラブルや争いが起こるリスクも大幅に低減されます。
さらに、公正証書遺言があれば、相続人以外の親族や孫などに対しても、財産を遺贈することができます。被相続人の意思を正確に反映できる手段として、公正証書遺言は非常に有効な方法です。

遺言書を作成するデメリット
遺言は、被相続人の意思を反映させる非常に有効な手段ですが、その内容によっては、かえって相続人同士の間でトラブルを招いてしまうケースもあります。たとえば、特定の相続人に偏った内容や、記載の不備が原因で、紛争に発展することも珍しくありません。
そのため、遺言書を作成する際には、法律の専門家に相談し、内容や形式に不備がないようしっかり整えることをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、遺言の効力が確かなものとなり、のちの相続手続きもスムーズに進められる可能性が高まります。
また、公正証書遺言などを作成するには、ある程度の手間や費用がかかります。とはいえ、その費用で将来的な相続人同士の争いを未然に防げたり、節税対策ができたり、煩雑な手続きを簡略化できたりすることを考えれば、十分に価値のある投資だと言えるでしょう。

Point
遺言書は作成するべき?
相続人の間で特に問題がなく、円満に話し合いが進められそうな場合には、必ずしも遺言書を作成する必要はありません。ただし、以下のような点も踏まえてご検討いただくと安心です。
まず、たとえ現時点では関係が良好でも、将来的に相続人の間で意見の対立が生じ、紛争へと発展する可能性はゼロではありません。遺言書がない場合、相続手続きは遺産分割協議を行う必要があり、相続人全員の署名と実印による押印が求められます。そのため、手続きが煩雑になり、時間も労力もかかってしまいます。
さらに、相続人の中に未成年者がいる場合には、その子に代わって意思決定を行う「特別代理人」を家庭裁判所に申立てる必要があり、手続きがさらに複雑になります。

遺言書を作成する際の注意点
(1)相続税を考慮する
相続税がかかる場合は、財産の分け方によって相続税額が大きく変わることがあります。
せっかくご家族のために遺言書を作成されるのであれば、相続税も考慮するとご家族に喜ばれるでしょう。(相続税の計算は税理士の業務範囲です。)
(2)遺留分を考慮する
相続人には最低限の財産をもらう権利が保障されており、その権利を「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺留分を無視したからといって遺言が無効になるわけではありませんが、遺留分より少ない財産しかもらえない相続人が多くの財産を取得する相続人に対して遺留分を主張すると、遺言より遺留分が優先されます。
そのため、遺留分も考慮して遺言書を作成するほうが相続人の間で紛争になるリスクを抑えられます。(付言事項として、お気持ちやその分け方とした事情を書くこともできます。)
相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。
Price
当事務所の遺言書作成の費用
| 遺言書作成費用 | 77,000円より |
|---|
料金はすべて税込です。