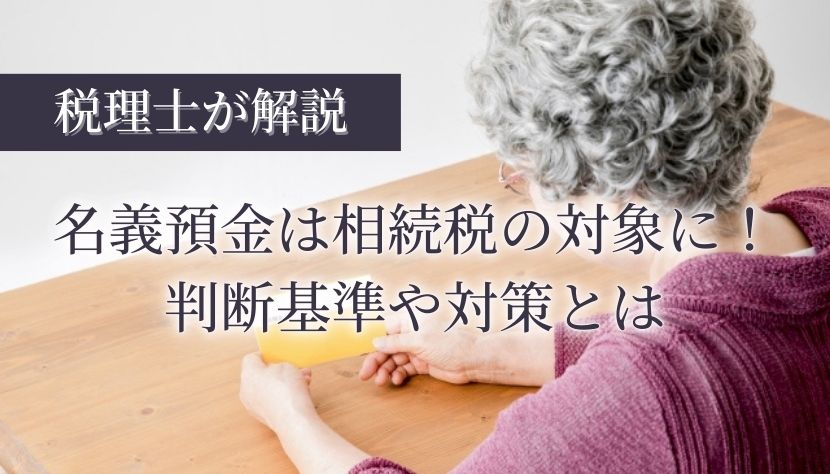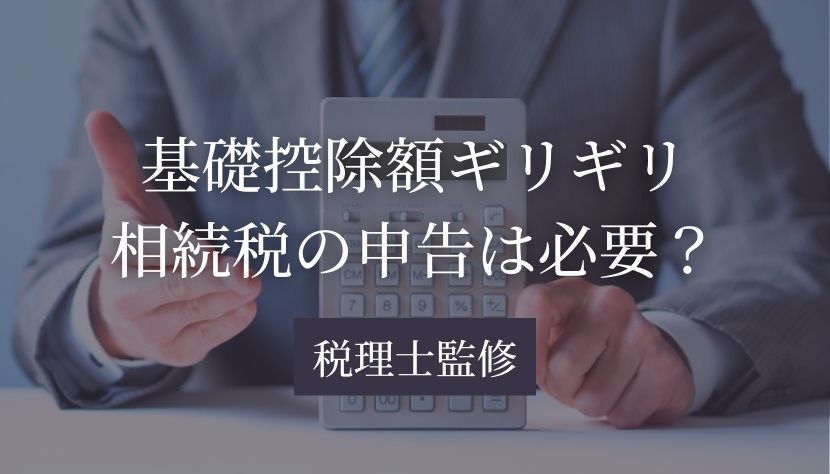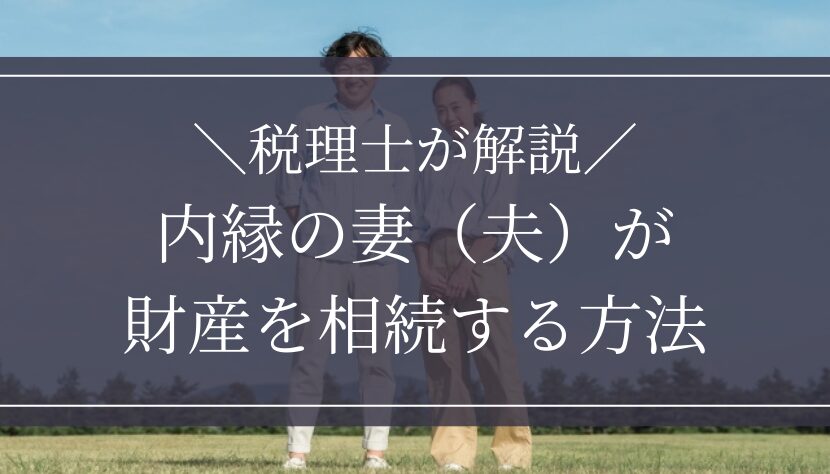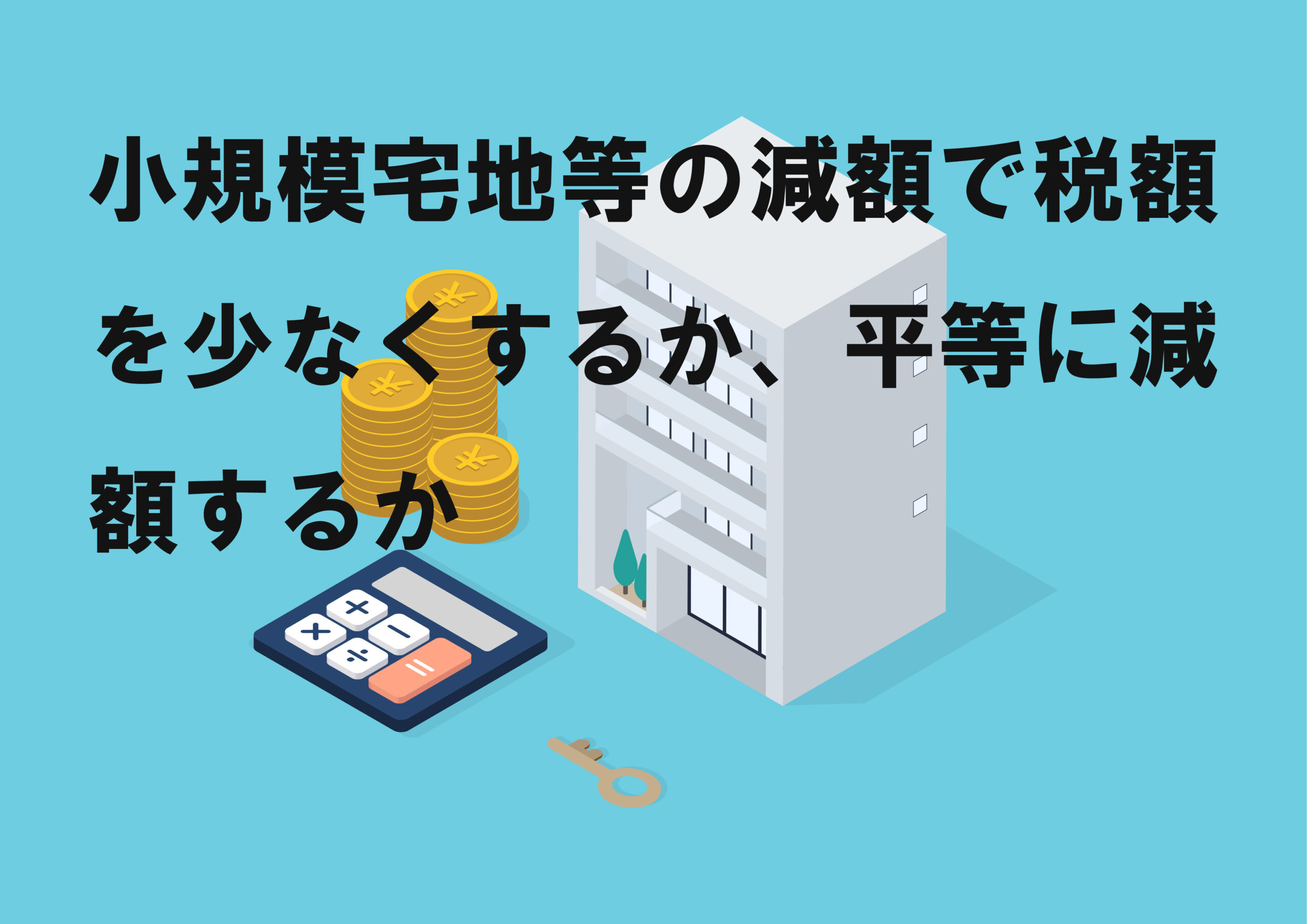Point
そもそも「相続税」とは?
相続税とは、亡くなった方の財産や、遺言によって財産を取得したときに生じる税金のことです。
亡くなった方を被相続人、財産を取得した人を相続人と呼びます。
一般的にその人の財産(遺産)は家族または遺言で指定された人に分配され、相続税はその分配された財産にかかります。
ただし、取得した財産が一定額以下であれば相続税はかからないので、申告の必要はありません。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
申告期限までに申告しなかった場合は加算税がかかり、期限までに納税しなかった場合には延滞税がかかります。
相続税は、遺産から葬式にかかった費用、非課税となる財産、借入金などの債務を差し引いた額をもとに計算します。

相続税対策とは?
01相続税額の試算
「相続税対策」をするには、まず相続税がいくらかかるかを試算することから始まります。
相続税の額により、するべき対策が異なります。
02相続税額の計算
- 財産の合計額から葬式費用・借入金・未払金等を控除します。
※3年以内の贈与財産や相続時精算課税の適用を受けた財産がある場合はここで加算します。
※3年以内の贈与財産の加算については税制改正により、段階的に7年以内の贈与財産の加算に順次延長されていきます。 - 次に相続税の基礎控除を計算します。
3,000万円+600万円× 法定相続人の数 - [ 1 ]<[ 2 ]の場合は、相続税はかかりません。
※[ 1 ]>[ 2 ]の場合は、[ 1 ]-[ 2 ]=課税される遺産総額となり、いずれかの相続人に相続税がかかる可能性が高いです。 - 課税される遺産総額×各人の法定相続分=「法定相続分の各相続人の取得価額」
「法定相続分の各相続人の取得価額」を下記の速算表に当てはめて、各人の相続税額を算出しその合計額が相続税の総額となります。
※相続税の計算で少々専門的になりますので3.やるべき相続対策へお進みください。
▼ 贈与税の速算表
スクロールできます
| 法定相続分の各相続人の取得価額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
03やるべき相続対策
- 相続税がかからない場合
「承継対策(家族間の争いを避けるには?)」のページへ - 相続税が少しかかる場合
「節税対策」、「承継対策(家族間の争いを避けるには?)」のページへ - 相続税が高額にかかる場合
「納税資金対策」、「節税対策」、「承継対策(家族間の争いを避けるには?)」のページへ
相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。
税金のかからない財産
- 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産・生命保険金の
「500万円×法定相続人の数」 - 死亡退職金(功労金)の、「500万円×法定相続人の数」
- 公共事業を行う者がもらった財産でその公共事業に使われることが確実なもの
- 業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)
- 業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)
合法的に相続税を節約する方法
- (1) 相続財産を圧縮する
- (2) 相続人を増加する
詳細については当事務所までお気軽にお問い合わせください。