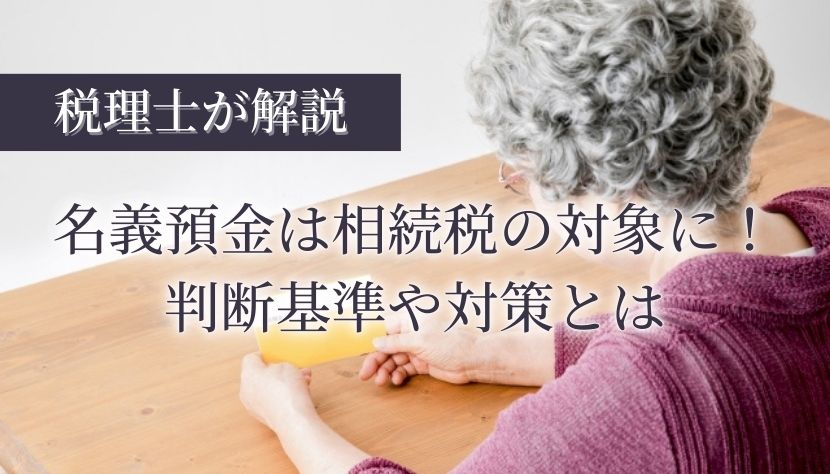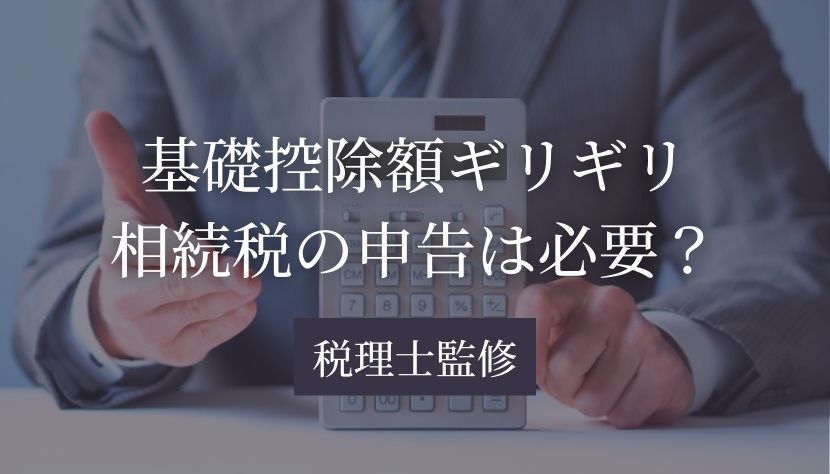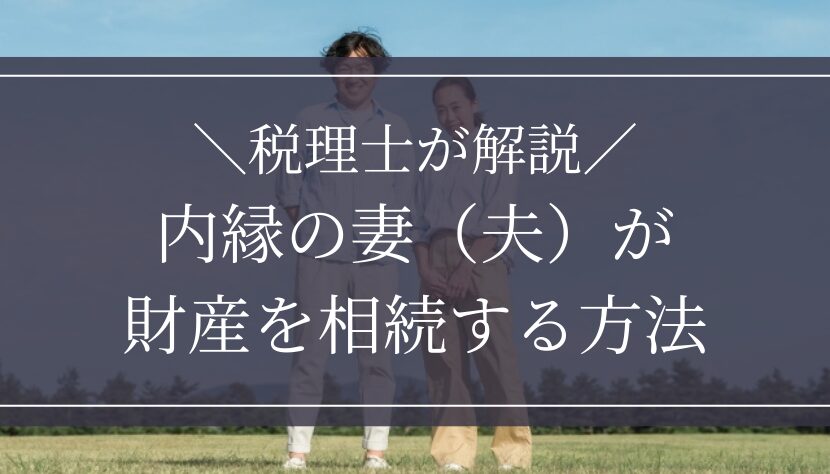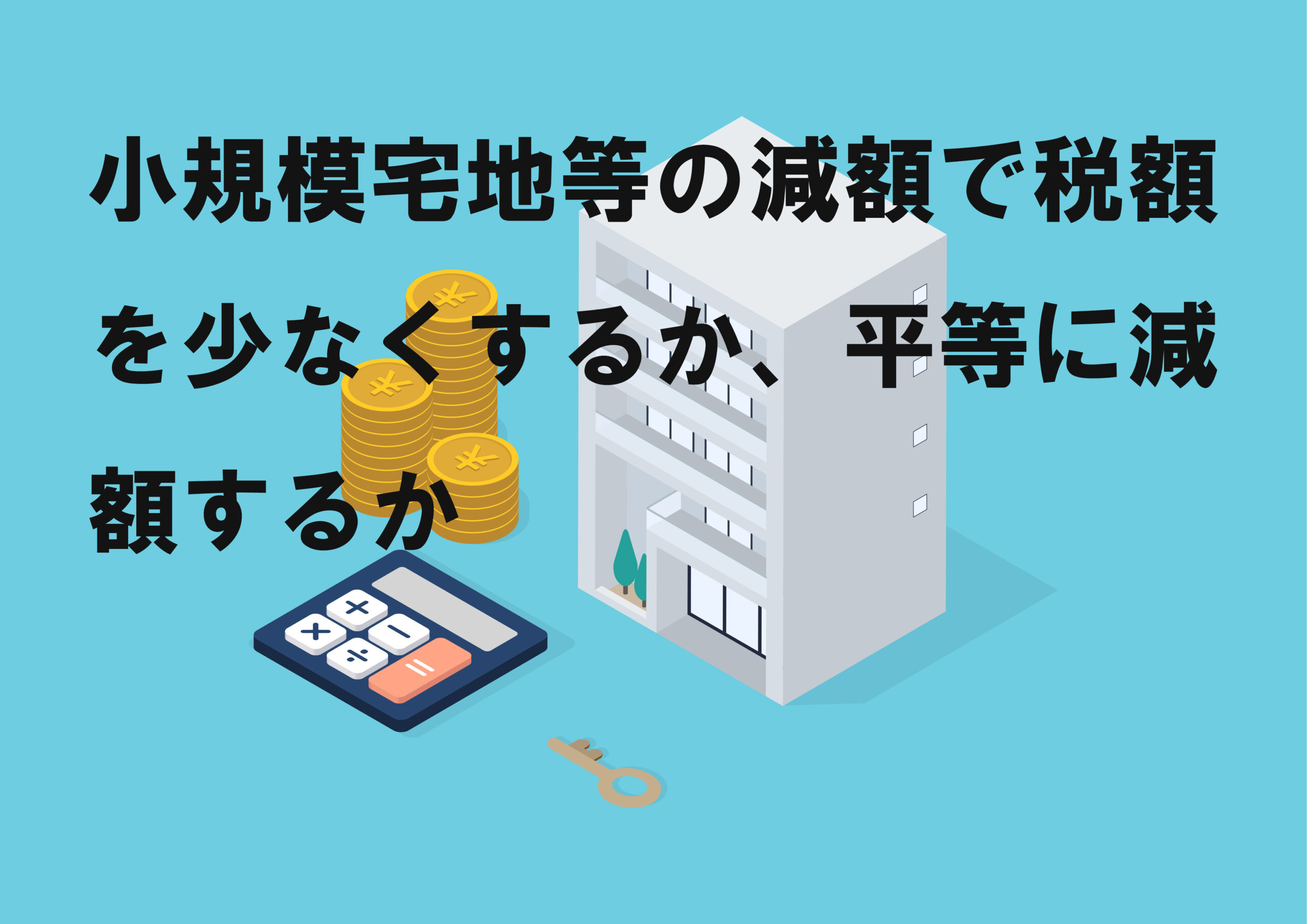Point
相続税とは
どんなときにかかる税金?
人が亡くなって、その人が所有していた財産を配偶者や子供などが相続したときに、財産の移転に対して相続税が課税されます。
「家族に財産を残すのにどうして税金がかかるの?」と思われるかもしれませんが、相続税には富の再分配という目的があります。たまたま親が資産家で労せず多額の遺産をもらえる人と、そうでない人がいるのは不平等と考えられるため、多額の遺産をもらった人からは税金を徴収して社会に還元しようという仕組みです。


相続税の申告が
必要な人・不要な人
人が亡くなったら相続税の申告が絶対に必要かというと、そうではありません。相続税には、大きな基礎控除があるからです。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算できます。たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円になります。遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないため申告も不要です。この基礎控除額を超えると、相続税の申告が必要となります。
相続税の申告・納付の
期限は10か月以内
相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。
たとえば、被相続人の死亡日が1月15日であれば、その年の11月15日が申告期限となります。申告期限内に申告しないと、あとで加算税などのペナルティが課されます。

申告期限までに
遺産の分割ができない場合
相続税の申告期限は、遺産の分割が申告期限内にできていない場合も延長されません。
この場合には、それぞれの相続人が民法で定められた法定相続分に従って、財産をもらったものとして相続税を計算し、申告します。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例は適用できません。(申告期限内に分割されていることが条件のためです。ただし、申告期限後3年以内に分割された場合等には適用できます。)また、申告後に財産が分割され、申告との差額が発生した場合は、実際の額に基づいて修正申告または更正の請求を行うことになります。
災害等の特別の事情がない限りは、10か月以内に必ず一度は相続税の申告をする必要があり、その後、もう一度申告をするという流れです。
小規模宅地等の特例・配偶者の税額の軽減
相続税の基礎控除額を超えたからといって、すぐに相続税がかかるわけではありません。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、最低限、住むところは守られるべきという趣旨から、配偶者や同居していた子供などが自宅を相続する場合には、敷地の330㎡までは相続税評価額を80%減額できる制度です。また、被相続人が生前に営んでいた事業に使われていた土地を親族が取得し、引き続き親族が事業を営むことなどで、同規定の適用を受けられる場合もあります。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、配偶者は被相続人とともに財産の形成に貢献してきたという趣旨から、配偶者の取得分が「遺産額×法定相続分」または1億6,000万円までなら、配偶者に相続税はかからない制度です。
※これらの規定は一定の期間内に遺産の分割をし、かつ相続税の申告書を提出しなければ適用できないので注意が必要です。
相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。
Price
当事務所の相続税申告の費用
| 相続税・贈与税の申告料金のお見積り | 無料 |
|---|---|
| 初回相談 | 30分 5,500円(ご契約の場合は申告料金より控除いたします) |
| 贈与税申告料 | 33,000円より |
| 相続税申告料 | 基本報酬110,000円+財産比例額 |
| 相続税の試算・節税対策の提案 | 110,000円より |
料金はすべて税込です。