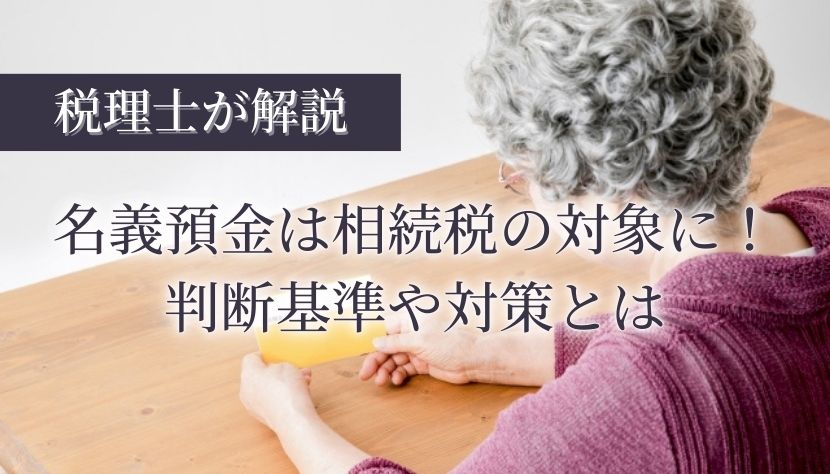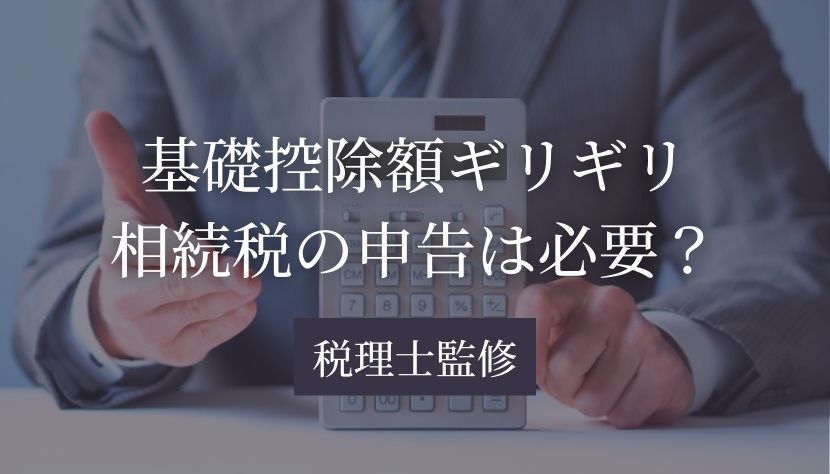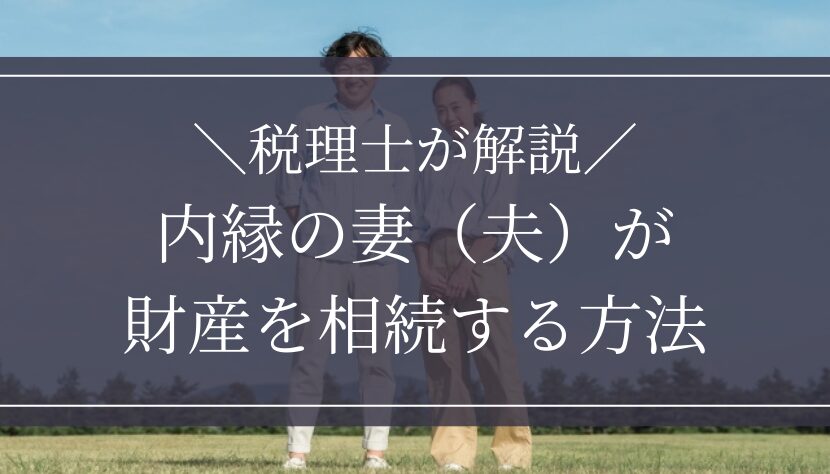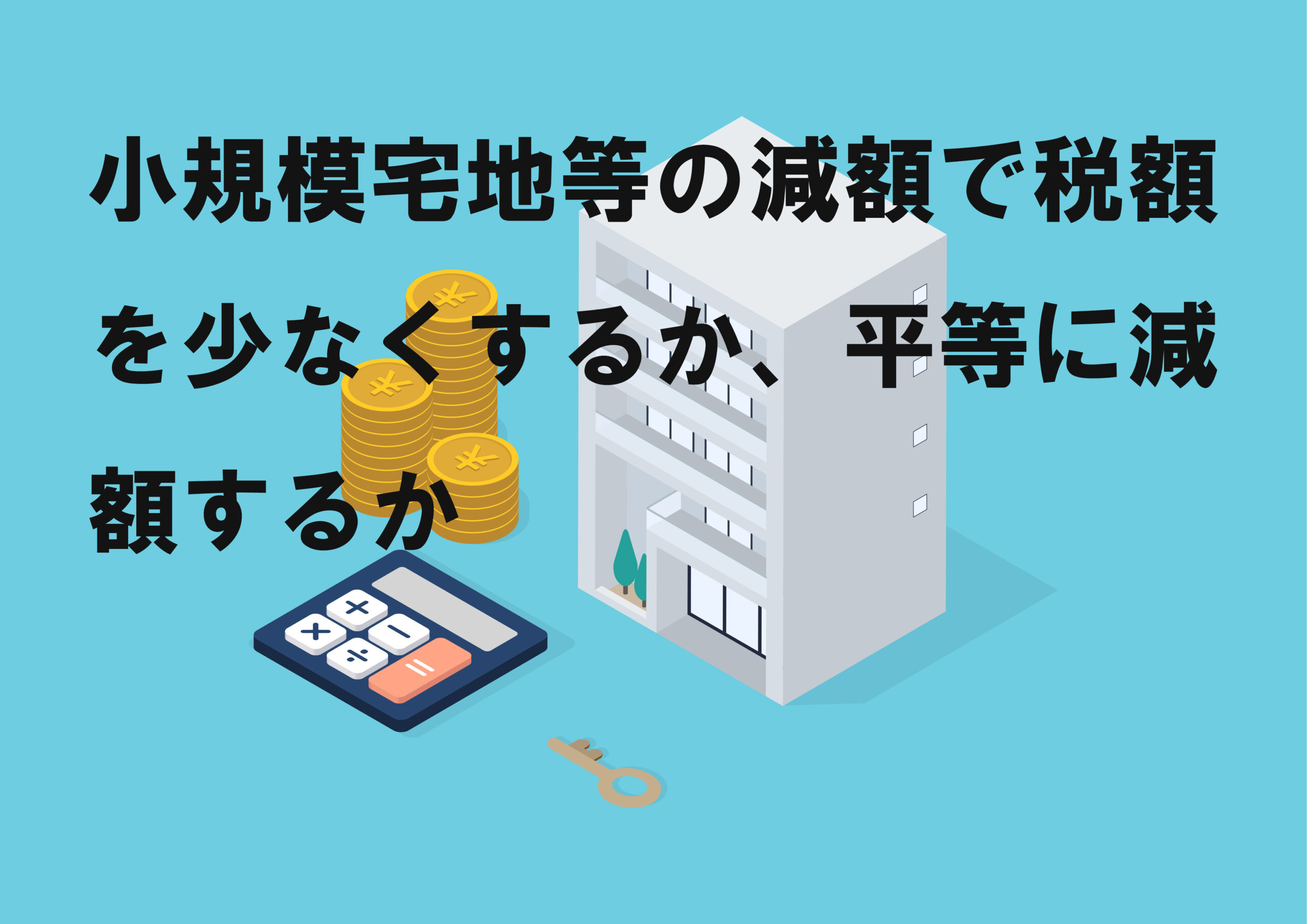Point
納税資金対策とは?
相続税は、10~55%と高い税率です。
相続財産に現預金等の納税資金が充分あればよいのですが、土地や建物などの不動産がほとんどで現預金が少ししかない場合、現金で納税することが困難となり、対応を間違えると最悪の場合、相続破産となるケースもあります。
節税対策も大切ですが、高額の相続税がかかる場合は承継対策と納税資金対策を中心に実行しながら、節税にも効果があるような取り組みをするのが最良の相続対策です。

生命保険金の利用
生命保険金は非課税枠があり、節税対策にもなり、継承対策にもなり、さらには納税資金対策にもなる優れものです。
当事務所では総合的に有利なアドバイスをさせていただきます。

土地・建物の処分
不動産が多い場合、不動産を処分して納税資金を確保しておく方法があります。
必ずしも第三者へ処分するだけでなく、承継者や会社に処分して納税資金を確保するのも一つの方法です。

退職金の利用
退職金にも非課税枠があり、節税対策になります。
会社名義で生命保険に加入し、相続時に退職金として支給できるようにしておけば、納税資金対策にもなります。

延納の利用
不動産など金銭以外の財産を多く相続したため、相続税を期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に金銭で一括納付することが困難な事由がある場合に、納付を困難とする金額を限度として年払いで納めることが認められています。(納付税額10万円超の場合)
担保が必要(延納税額が100万円超・延納期間が3年超の場合)で、利子税がかかるほか、納付期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を受ける必要があります。

物納の利用
延納によっても相続税を金銭で納付することが困難な事由がある場合、納付が困難である金額の限度内で物納(土地や株式などで相続税を納付)することができます。
対象の財産は公債、不動産等、 社債・株式等、動産で、抵当権が付いた財産や係争中の財産は物納できません。
納付期限までに物納申請書を提出し、税務署長の許可を受ける必要があります。
なお、相続した金銭だけでなく、相続人自身の預金があれば物納は許可されません。
近い将来に収入があるかどうかも判定されるため、まとまったお金でなくても一定の収入があり、延納できる状態の場合も認められません

納税猶予の利用
農地や山林、同族会社は、後継者が相続税の負担の重さによって経営困難となり、農地や山林の売却、会社の閉鎖を余儀なくされる可能性があります。
その救済措置として、農地や山林、非上場株式は一定の条件を満たすことにより相続税が猶予(免除)されるため、後継者は高額な相続税を支払うことなく経営を承継できます。
あなたの財産状況や家庭事情などを考慮して、無理のない納税資金対策を検討しましょう。

相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。