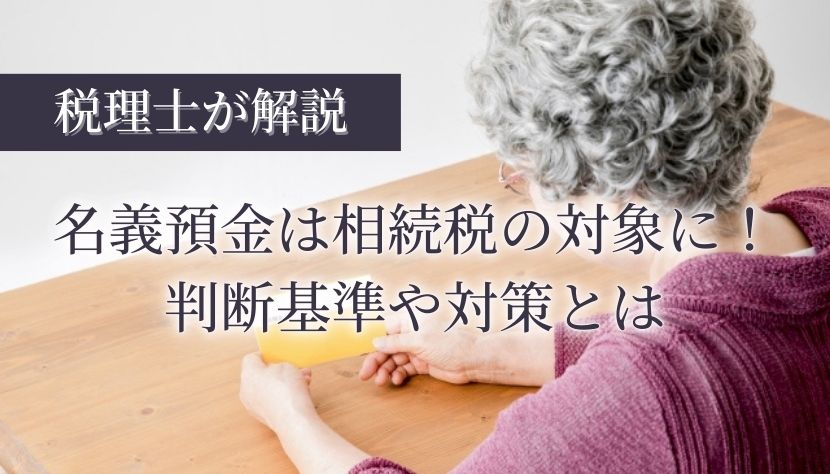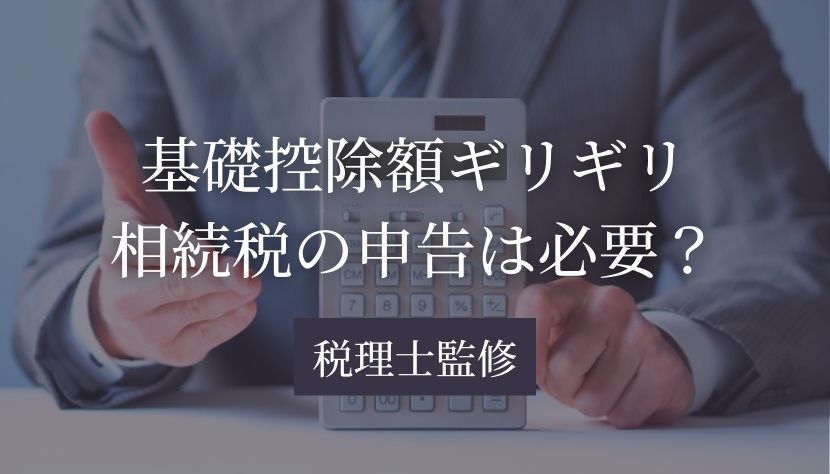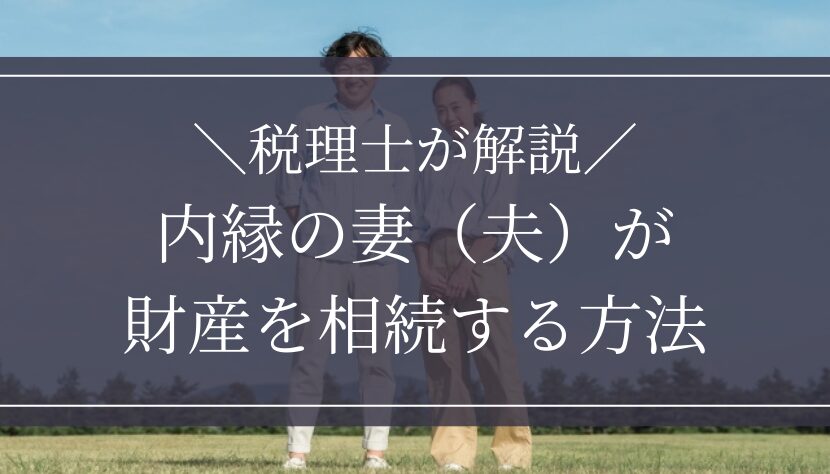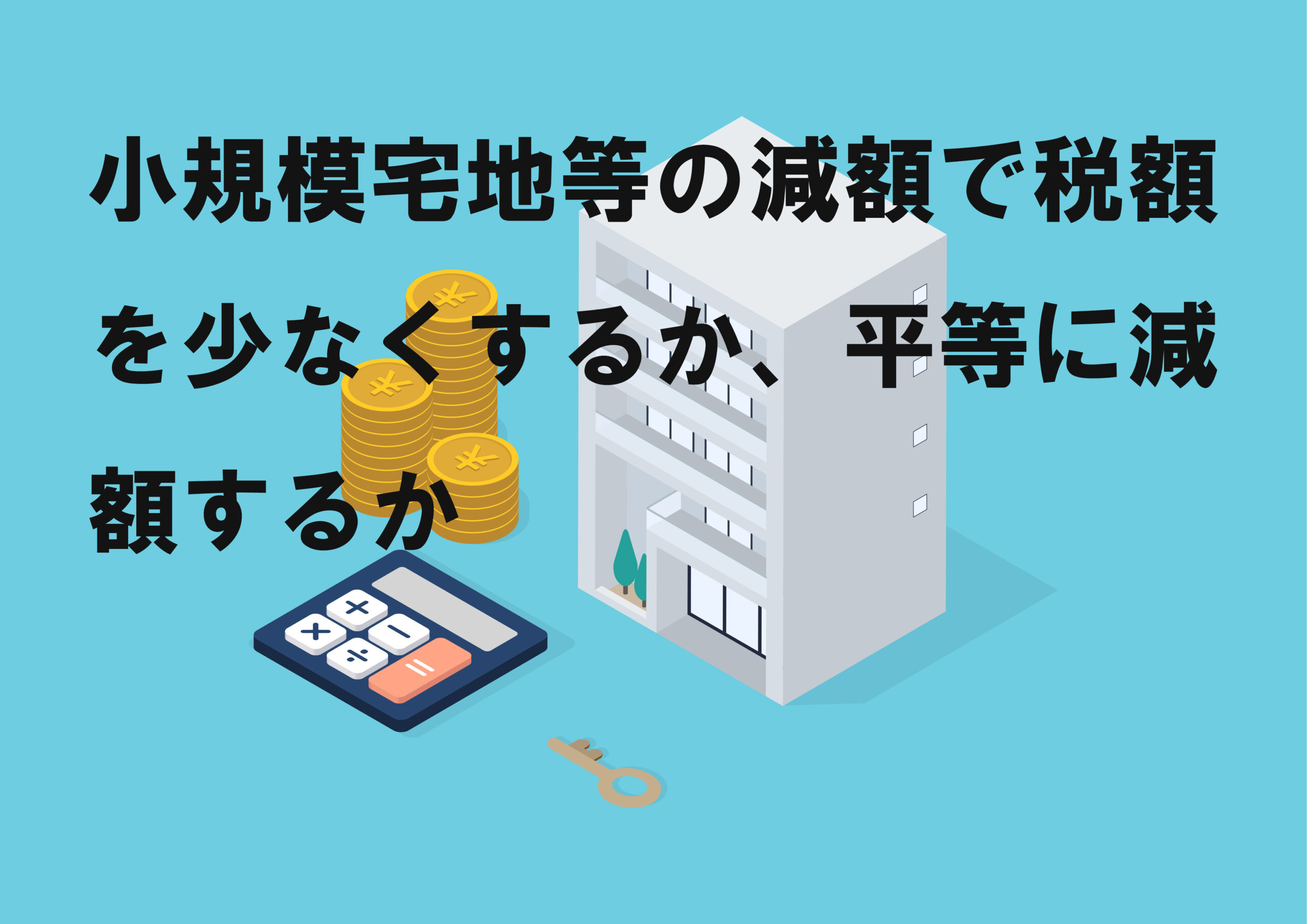Point
節税対策とは?
相続税には、事前に対策を講じることで節税できるケースが多くあります。
たとえば、生前贈与や不動産の活用、生命保険の活用など、さまざまな方法がありますが、どの対策にも共通して大切なのは早めに準備を始めることです。
というのも、相続がいつ起きるかは誰にもわかりません。
一方で節税対策には手続きや時間が必要なものが多く、効果が現れるまでに一定の期間を要することもあります。また、被相続人が高齢になると判断力や行動力が低下し、思うように対策を進められなくなるケースも少なくありません。だからこそ、相続対策は「いつか」ではなく「今から」。
相続税の負担を軽減し、大切な財産を確実に引き継いでいくためにも、早めの行動を強くおすすめします。
相続税の補完的な税金として贈与税があり、贈与税も最高税率55% と非常に高い税金です。

生前贈与
生前贈与をすることによって相続税(相続財産)を減らせます。
生前贈与には贈与税がかかりますが、下記のような制度を利用すれば贈与税の負担なく、または低額の贈与税で贈与できます。
- 毎年、贈与税の基礎控除を利用する
(贈与する財産が年間110万円までの場合は、贈与税がかかりません) - 親から子・孫(18歳以上)への住宅資金贈与の特例の利用
令和8年12月31日までで、500万円又は1,000万円を限度(年度や要件により異なります)として贈与税がかかりません。 - 直系尊属(父母や祖父母など)から30歳未満の者への教育資金の一括贈与の特例の利用
令和8年3月31日までで、1,500万円を限度として贈与税がかかりません。 - 父母や祖父母から子や孫(18歳以上50歳未満)への結婚や子育資金の一括贈与の特例の利用
令和9年3月31日までで、1,000万円を限度として贈与税がかかりません。 - 結婚20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与税の特例の利用
2,000万円を限度として贈与税がかかりません。 - 相続時精算課税制度の利用
適用を受けると2,500万円までの部分については贈与税がかかりません。

上記の特例規定には、申告期限までに贈与税の申告書を提出しなければ適用されないものがあります。詳しくは当事務所までご相談ください。
生命保険の利用
生命保険金には、相続時の非課税枠があります。
[非課税枠] 法定相続人の数×500万円
(例)相続人が妻と子供2人の場合、3人×500万円=1,500万円
相続人が1人なら500万円まで、相続人が3人なら1,500万円までの生命保険金には相続税がかかりません。
また、生命保険金は現預金で受け取れるため、納税資金や生活資金にできるほか、相続放棄しても受け取ることができます。
当事務所では、生命保険について総合的に有利なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

退職金の利用
ご自身で会社(法人)を経営されている場合は、法人名義でご自身の生命保険(事業保険)に加入し、亡くなられたときに保険金を原資とした退職金を支給できるようにしておけば、退職金にも非課税枠があり、生命保険金と同様に納税資金や相続人の生活資金とすることができます。
[非課税枠] 法定相続人の数×500万円
(例)相続人が妻と子供3人の場合、4人×500万円=2,000万円
相続人が1人なら500万円まで、相続人が3人なら1,500万円までの退職金には相続税がかかりません。ご存命中においても、事業保険は会社の経費に計上できるので会社の法人税の節税対策にもなります。

相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。
土地・建物の有効利用
小規模宅地等の特例の適用を受けると、最大で土地の価額の80%を減額できます。
受けられるのは居住用と事業用の土地で、面積の制限があります。
また、空き地にマンションやアパートを建築すると、土地や建物の建築価額の評価が下がり、小規模宅地等の特例も50%減で適用できるため、節税対策になります。
ただし、貸家経営はリスクを伴う事業でもあるので、実行には検討が必要です。

養子縁組の利用
養子縁組をして相続人の数を増やすことも相続税対策となります。
嫁や孫などを養子にし、法定相続人を増やすと基礎控除額が増え、累進税率が下がり、生命保険金や退職金の非課税枠も大きくなります。
ただし、相続税額の計算上、法定相続人に含める養子の数には制限があり、実子がいる場合は1 人、実子がいない場合は2人までです。
養子縁組は節税だけでなく、相続権のない人に財産を相続させるための手段としても有効で、お世話になったお嫁さんや可愛がっているお孫さんに財産を与えたいときなどには、養子縁組の制度を利用するとよいでしょう。

相続後の対策
節税対策は相続前だけではありません。
相続後に財産をどう分割し、どう評価するかによっても税額は大きく変わります。
詳しくはぜひ、当事務所までお問い合わせください。

贈与税・相続税の納税猶予制度の活用
農地や山林、自らが経営する会社の非上場株式で一定のものには、後継者にとって大きな負担となる贈与税や相続税を猶予したり免除したりすることで、円滑に経営を承継させる税制上の優遇措置があります。制度の適用を受けるためには、決められた申告要件を満たす必要があり、事前に綿密な検討や手続きなどを要します。
特に非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度は平成21 年に制定された比較的新しい制度であり、適用の事例もまだ多いとは言えず、さらに後継者等に課せられる要件も厳格です。
ただし、適用を受けることができれば、後継者は税負担を大幅に軽減できます。

その他節税対策
お墓や仏壇には相続税がかからないため、生前に購入しておくと購入費分だけの相続財産を減らすことができます。
相続後に遺産から購入しても控除できないので、まだお墓や仏壇がない人は節税対策になります。
また、子供夫婦と同居している自宅などが老朽化していて建て替えやリフォームを検討している場合には、建て替えやリフォームすることによって建築費用の評価が約70%に下がり、現金で所有している場合よりも節税効果が得られます。
借入による建て替えやリフォームでも同様です。
さらに、生活費や教育費は非課税で贈与できるため、同居している場合の生活費は父、祖父、祖母などが支払うようにすれば、贈与税の負担なく贈与することができます。
他にも財産状況や家庭事情などによって節税対策は異なるので、詳しくはぜひ、当事務所までお問い合わせください。

相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。