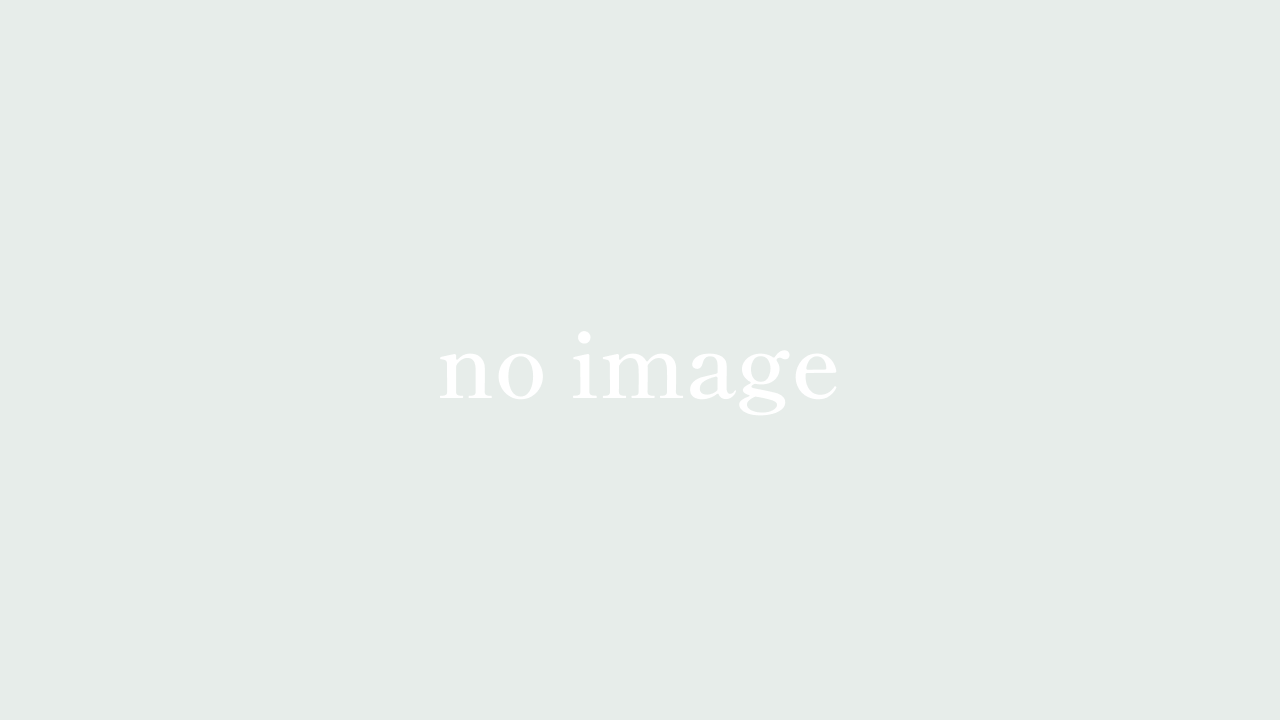【相続権がない内縁の妻(夫)が財産を相続する方法】内縁関係(事実婚)の相続や注意点を税理士が解説
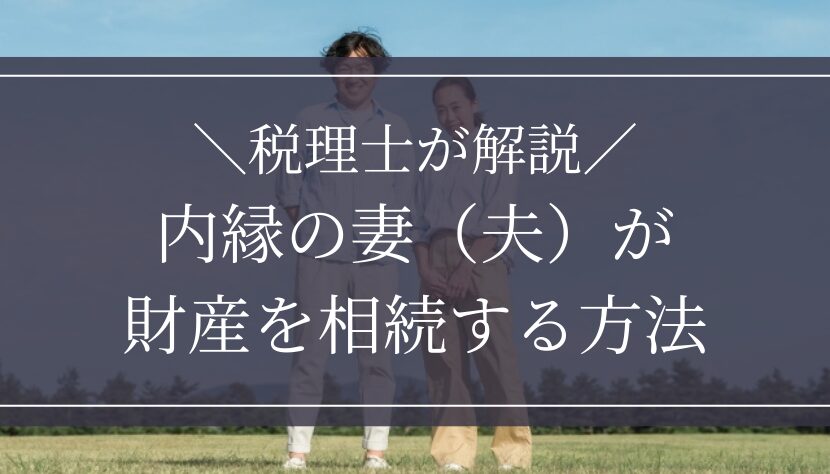
内縁の夫婦(事実婚)には、お互いにパートナーの財産を相続する権利がありません。
よって、内縁の妻(夫)が財産を相続するためには生前に対策しておく必要があります。
本記事では、内縁の妻(夫)に財産を相続する方法をわかりやすく解説します。
注意点やよくある質問も解説するので、内縁の妻に財産を残したい方や、内縁の夫の財産を相続できるように対策しておきたい方はぜひお役立てください。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
内縁の妻(夫)には相続権がない
内縁の夫が亡くなった場合、残された内縁の妻にはパートナーである夫の財産を相続する権利(相続権)はありません。
反対に、内縁の妻が亡くなった場合も、内縁の夫には相続権はありません。
民法により法定相続人(法的に相続する権利がある人)の範囲が定められており、内縁関係の妻や夫は法定相続人に含まれないためです。
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子ども |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
事実婚を選択し、たとえ何十年連れ添ったとしても、法律上の婚姻関係が成立していなければ財産を相続することはできません。
内縁の妻(夫)との子どもは相続人になる
内縁の妻(夫)との子どもがいる場合、父親である内縁の夫が子どもを認知していれば、子どもは内縁の夫の法定相続人になります。
父親が認知をした子どもとは、法律上の親子関係が成立するためです。
たとえば、内縁の夫に離婚した前妻との子どもAが1人と、内縁の妻との子どもBが1人いたとします。
内縁の夫が子どもBを認知していれば、子どもAと子どもBの両方が内縁の夫の法定相続人になります。
反対に、内縁の夫が子どもBを認知していなければ、子どもAのみが内縁の夫の法定相続人になります。
なお、子どもAと子どもBの両方が法定相続人になる場合、子どもAと子どもBの相続割合は同じです。
内縁関係の妻との子どもだからといって相続割合が少なくなることはありません。
内縁の妻(夫)が財産を相続する4つの方法
内縁の妻(夫)が財産を相続する方法は、以下の通りです。
1.遺言書を作成する
2.生前贈与をする
3.生命保険を活用する
4.特別縁故者になる
生前に対策しておく必要があるため、夫婦で話し合い、最善の方法を検討しましょう。
1.遺言書を作成する
遺言書を作成し、内縁の妻(夫)に財産を引き継がせる内容を記載しておけば、内縁の妻(夫)は財産を相続できます。
法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことを「遺贈(いぞう)」と呼びます。
遺言書がある場合、原則として遺言の内容に従って遺産分割するため、内縁の妻(夫)が財産を相続する方法として最も一般的であり、有効な方法です。
なお、遺言書は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に分かれますが、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
自筆証書遺言は内容や形式に不備があった場合、法的に無効となるリスクがあるためです。
また、遺言書を作成するときは、他の相続人の遺留分を侵害しないようにも注意しなければなりません。
詳しくは後ほど解説します。
2.生前贈与をする
内縁の妻(夫)へ、生前に財産を贈与しておくのも有効な方法です。
贈与税には110万円の基礎控除があり、毎年110万円までは贈与税がかからないため、税金の負担もなく確実に財産を渡すことができます。
ただし、贈与は財産をあげる人ともらう人がお互いに意思表示をし、両者の合意によって成立します。
実際に贈与があったことを証明するために、必ず贈与契約書を交わしましょう。
また、一定の時期に一定の金額を毎年贈与すると、税務署に定期贈与と判断される場合があります。
たとえば、1,000万円を10回に分けて、内縁の妻(夫)に毎年100万円を贈与したとします。
本来であれば100万円の贈与は非課税になりますが、税務署に「最初から1,000万円を贈与すると両者で約束されていた」と判断された場合、1,000万円から110万円の基礎控除額を差し引いた890万円に贈与税がかかります。
贈与するごとに贈与契約書を交わし、贈与する時期や金額を一定にしないよう注意してください。
3.生命保険を活用する
生命保険金の受取人を内縁の妻(夫)に指定すると、内縁の妻(夫)は生命保険金の全額を受け取れます。
そもそも生命保険金は受取人の固有の財産として扱う(相続財産ではない)ため、遺産分割の対象にならず、遺留分の心配も不要です。
ただし、生命保険金は相続税の対象になり、内縁の妻(夫)のような法定相続人以外の人が受け取った場合、生命保険金の非課税枠が使えない点には注意しなければなりません。
※法定相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税になります。
また、詳しくは後ほど解説しますが、内縁の妻(夫)に相続税がかかる場合は相続税の2割加算が適用され、通常より相続税の負担が大きくなる点にも注意が必要です。
4.特別縁故者になる
生前に対策できる方法ではありませんが、残された内縁の妻(夫)が特別縁故者と認められた場合、内縁の妻(夫)は財産を相続できます。
特別縁故者とは、被相続人(亡くなった人)に法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係があったとして財産を取得できる人のことです。
具体的には、以下のような人が特別縁故者と認められます。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他、被相続人と特別の縁故があった者
なお、特別縁故者と認められるためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」をする必要があります。
| 申立てに必要な費用 | ・収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手 |
|---|---|
| 申立てに必要な書類 | ・申立書 ・申立人の住民票または戸籍附票 |
申立てには一定の期間や複雑な手続きが必要となるため、先述の生前に対策できる方法を検討したほうがよいでしょう。
内縁の妻(夫)が相続するときの注意点
内縁の妻(夫)が相続するときは、以下3点に注意しましょう。
・財産を相続したら相続税がかかる
・他の相続人の遺留分を侵害しない
・配偶者居住権は適用できない
財産を相続したら相続税がかかる
内縁の妻(夫)が財産を相続した場合も、相続税がかかる可能性があります。
法律上の配偶者であれば、相続税を減額できる特例や控除を適用できますが、内縁の妻(夫)は特例や控除の対象外となります。
よって、相続税が高額になる恐れがあるため、内縁の妻(夫)が相続する場合は税金面でも生前の対策が重要です。
▼相続税の計算の注意点
※内縁の妻(夫)が相続する場合
・基礎控除の法定相続人の数に含まれない
・相続税の配偶者控除を適用できない
・小規模宅地等の特例を適用できない
・生命保険金の非課税枠を適用できない
・死亡退職金の非課税枠を適用できない
・相続税の2割加算が適用される など
相続税の基礎控除を詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
相続税の基礎控除を税理士がわかりやすく解説
相続税の配偶者控除を詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
相続税の配偶者控除を税理士がわかりやすく解説
他の相続人の遺留分を侵害しない
内縁の妻(夫)以外に相続人がいる場合、遺言書を作成するときは他の相続人の遺留分に配慮しましょう。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。
他の相続人の遺留分を侵害してしまう(遺留分を下回る遺産しか相続できない)と、遺言書がトラブルの火種となる恐れがあります。
よって、内縁の妻(夫)が財産を相続するために遺言書を作成する場合は、遺留分を侵害しないよう遺産の分け方に注意が必要です。
なお、相続税がかかる場合は遺産の分け方で税額が変わるため、遺言書を作成する前に税理士へ相談するとよいでしょう。
配偶者居住権は適用できない
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた家に、残された配偶者が無償で住み続けられる権利のことです。
相続法改正により令和2年4月1日から配偶者居住権を設定できるようになったものの、内縁の夫婦には適用できない点に注意しましょう。
過去には内縁の夫婦でも居住権や賃借権を認めた判例が存在するため、一定の保護は受けられるとも考えられますが、必ずしも認められるとは限りません。
なお、賃借権とは、賃料を支払って借りたものを使用できる権利のことです。
よって、賃貸マンションやアパートなどに内縁の夫婦で同居している場合も含め、残された内縁の妻(夫)が安心して生活を続けられるように、遺言書に家の所有権や賃借権に関しても記載しておくことをおすすめします。
【Q&A】内縁関係(事実婚)の相続に関するよくある質問
ここからは、内縁関係の相続に関するよくある質問にお答えします。
内縁の妻(夫)はマンションを相続できる?
内縁の妻(夫)には相続権がないため、マンションを相続することはできません。
たとえば、内縁の夫が所有しているマンションに夫婦で同居しており、夫の死後に内縁の妻がマンションを相続するためには、遺言書を作成しておく必要があります。
内縁の妻(夫)の相続割合は?
内縁の妻(夫)の相続割合はありません。
繰り返しになりますが、内縁の妻(夫)に相続権はなく、法定相続分も遺留分もありません。
また、寄与分や特別寄与料も認められないため、内縁の妻(夫)が財産を相続するためには生前の対策が必要です。
※寄与分=被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に他の相続人より多い割合で財産を相続できる制度
※特別寄与料=被相続人を無償で介護するなど財産の維持や増加に貢献した場合に、相続人に対して貢献度に応じた金銭を請求できる制度
内縁の妻(夫)にはどのような権利がある?
内縁の妻(夫)でも、所定の要件を満たしている場合は以下のような権利が認められます。
・遺族年金
・埋葬料・葬祭費
・死亡退職金
大切なパートナーの将来の生活を守るためにも、相続に向けた対策は早めに進めておきましょう。
内縁関係(事実婚)の相続なら税理士法人吉本事務所へ

・内縁の妻に財産を残したい
・内縁の夫の財産を相続できるように対策しておきたい
・他の相続人とのトラブルが起こらないように進めたい
・どのような遺言書を作成すればよいかわからない
など、内縁関係の相続のお悩みは税理士法人吉本事務所にご相談ください!
当事務所では相続専門の税理士が、相続税・贈与税の申告をはじめ、生前対策、遺言書作成など、各種相続手続きのご相談やご依頼をお受けしています。
長年の経験と知識を活かした相続税対策を強みとし、お客様にとってベストな選択をご提案いたしますのでどうぞご安心ください。
また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、内縁関係の相続に関する幅広いお悩みに対応可能です。
お忙しい場合はオンライン相談もお受けしているので、まずはお気軽に税理士法人吉本事務所までお問い合わせください。
当事務所のホームページはこちらから
無料お見積り・お問い合わせはこちらから
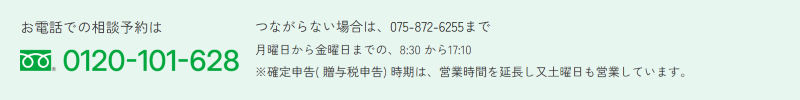
まとめ
内縁の夫婦は法律上の婚姻関係が成立していないため、パートナーの財産を相続する権利(相続権)はありません。
よって、遺言書を作成したり生前に財産を贈与したりなど、相続が発生する前に対策しておくことが重要です。
内縁の妻(夫)の他にも相続人がいる場合は遺留分に注意し、また相続税を抑えて財産を引き継げるよう専門家に相談しながら最善の方法を検討しましょう。