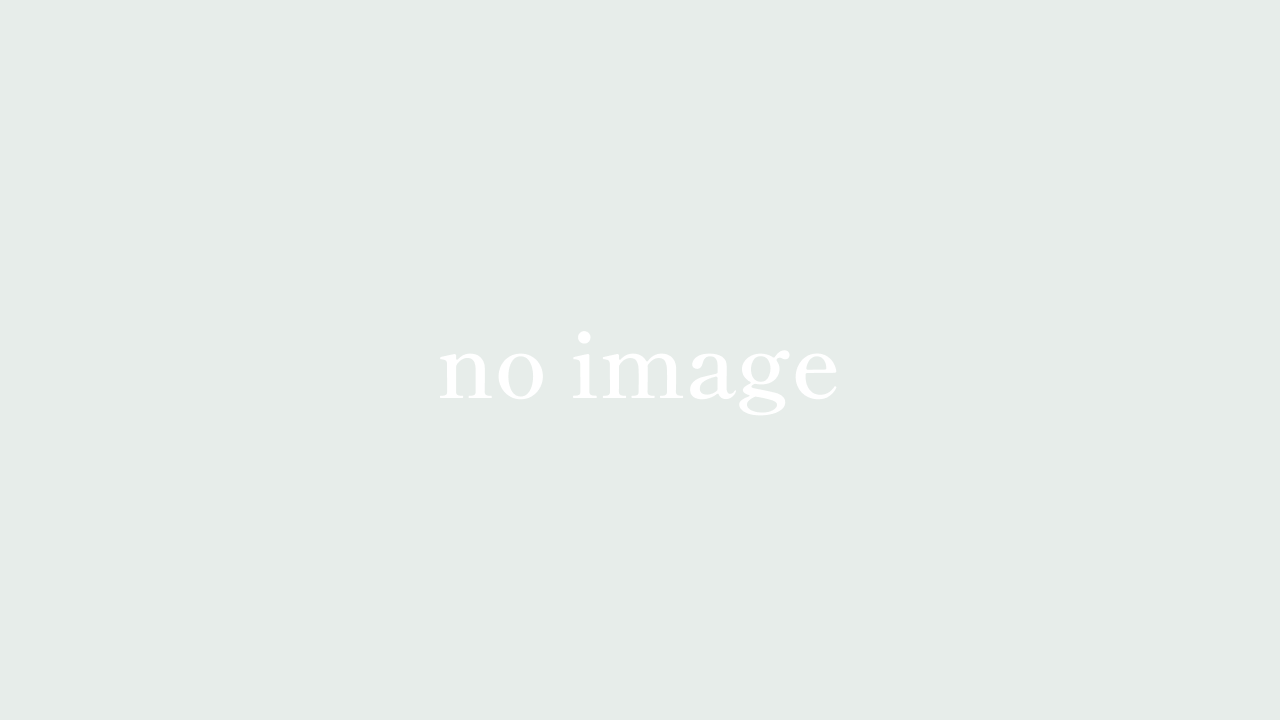孫に財産を相続させる方法は?孫が法定相続人になるケースや非課税で財産を贈与する方法も税理士が解説

結論から言えば、孫は特定のケースを除き、祖父母の法定相続人にはなれないため、祖父母の財産を相続することはできません。
ただし、生前に対策しておけば孫へ財産を引き継がせることはできます。
本記事では、孫が法定相続人になるケースや、孫に財産を相続させる方法をわかりやすく解説します。
非課税で孫に財産を贈与する方法も解説するので、孫に財産を残したい方や税金の負担を抑えて財産を渡したい方はぜひお役立てください。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
孫は原則として法定相続人にはなれない
孫は原則として、祖父母の法定相続人にはなれません。
よって、孫は祖父母の財産を相続することはできません。
民法により法定相続人(法的に相続する権利がある人)の範囲が定められているためです。
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子ども |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
被相続人(亡くなった人)に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と第1順位の子どもが法定相続人になります。
配偶者がいない場合、第1順位の子どものみが法定相続人になります。
第2~3順位の人は、上位の人がいない場合のみ法定相続人になる仕組みです。
ただし、以下のケースでは孫が祖父母の法定相続人になります。
・孫と養子縁組をしている
・代襲相続が発生している
孫が法定相続人になるケース
孫が祖父母の法定相続人になる2つのケースを解説します。
孫と養子縁組をしているケース
祖父母が孫と養子縁組をしている場合、孫は祖父母の子どもとして法定相続人になります。
養子縁組により法律上の親子関係が成立しており、実の子どもと同じ権利が認められるためです。
よって、養子縁組をした孫(孫養子)は第1順位の子どもとして、祖父母の法定相続人になります。
孫と養子縁組をしているケースで孫が相続できる割合
孫が相続できる割合は、祖父母の子どもと同じです。
祖父母の子ども(孫養子含む)が2人以上いる場合は、以下の割合を全員で均等に分けます。
| 被相続人に配偶者がいる場合 | 配偶者2分の1 子ども(孫養子含む)2分の1 |
|---|---|
| 子ども(孫養子含む)のみの場合 | 1 |
子どもの範囲は、実子、養子、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども)、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)を含むため、孫養子と祖父母の子どもが相続する割合は同じになります。
代襲相続が発生しているケース
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、法定相続人が死亡している場合などで、相続の権利が引き継がれることです。
代襲相続が発生している場合、孫は祖父母の法定相続人になります。
たとえば、祖父が亡くなったとします。
本来であれば、祖父の子ども(孫の親)が法定相続人になりますが、子どもが祖父よりも先に亡くなっている場合、孫が子どもの代わりとして法定相続人(代襲相続人)になります。
代襲相続が発生しているケースで孫が相続できる割合
相続の権利はそのまま引き継がれるため、孫が相続できる割合は祖父母の子どもと同じです。
祖父母の子ども(代襲相続人になった孫含む)が2人以上いる場合は、以下の割合を全員で均等に分けます。
| 被相続人に配偶者がいる場合 | 配偶者2分の1 子ども(代襲相続人になった孫含む)2分の1 |
|---|---|
| 子ども(代襲相続人になった孫含む)のみの場合 | 1 |
なお、代襲相続が発生したことで、配偶者や子どもの兄弟姉妹(孫の親の兄弟姉妹)が相続する割合が変わることはありません。
孫に財産を直接相続させる3つの方法
孫に祖父母の財産を直接相続させる方法は、以下の通りです。
1.遺言書を作成する
2.孫と養子縁組をする
3.生命保険を活用する
1.遺言書を作成する
遺言書を作成して孫を受遺者に指定すれば、孫に財産を相続(遺贈)させることができます。
受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人を指し、遺言によって財産を渡すことを遺贈と呼びます。
遺言書がある場合、原則として遺言の内容が優先されるため、誰に、何を、どの割合で引き継がせるか、などの希望を具体的に実現できる方法です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の相続分が保証されています(遺留分)。
遺言書を作成するときは、遺留分に配慮しなければトラブルの火種となりかねないので注意しましょう。
なお、遺言書は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に分かれます。
自筆証書遺言は不備があった場合、法的に無効となるリスクがあるため、公正証書遺言を作成するほうがよいでしょう。
遺言書を作成する場合の孫が相続できる割合
原則として遺言の内容が優先されるため、孫が相続できる割合は遺言の通りです。
ただし、先述の通り他の相続人の遺留分には配慮する必要があります。
2.孫と養子縁組をする
孫と養子縁組をすれば、祖父母の子どもとして孫に財産を相続させることができます。
冒頭でお伝えしたように、養子縁組により法律上の親子関係が成立し、実の子どもと同じ権利が認められるためです。
ただし、孫養子には相続税が2割加算される点に注意する必要があります(相続税額の2割加算)。
なお、代襲相続が発生しており、孫養子が代襲相続人になるケースでは2割加算の対象にはなりません。
詳しくは後ほど解説します。
3.生命保険を活用する
生命保険金の受取人を孫に指定すれば、孫は自分の財産として生命保険金を受け取れます。
ただし、この方法が有効なケースは以下に当てはまる場合に限られます。
・孫と養子縁組をしているケース
・代襲相続が発生しているケース
・そもそも相続税がかからないケース
通常、法定相続人ではない孫が受け取る生命保険金には非課税枠が適用されず、また相続税が2割加算されるためです。
基本的には生命保険金の受取人を孫に指定することは避けたほうがよいでしょう。
相続税対策には孫への生前贈与がおすすめ
孫に財産を残したいなら、相続させるより生前贈与をするほうが得と言えます。
贈与税の非課税枠を活用すれば、贈与税がかかることなく孫に財産を渡せるほか、相続税の節税にも効果があるためです。
孫を含め、財産を相続する人の負担が減り、また財産を守ることにもつながります。
また、相続税がかからない場合でも、生前贈与なら孫へ確実に財産を残せます。
非課税で孫に財産を贈与する5つの方法
非課税で孫に財産を贈与する方法は、以下の通りです。
1.暦年課税を活用する
2.教育資金の一括贈与の特例を適用する
3.結婚・子育て資金の一括贈与の特例を適用する
4.住宅取得等資金の非課税の特例を適用する
5.相続時精算課税制度を活用する
詳しく解説します。
1.暦年課税を活用する
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税を計算する方法を指し、贈与税の課税方法の一つです。
暦年課税には年110万円の非課税枠(基礎控除)があるため、年110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。
毎年110万円以内の贈与を繰り返せば、非課税で孫に財産を渡せるということです。
ただし、税務署に定期贈与(一定の期間に一定の金額を贈与すること)と判断されると、贈与した合計額に贈与税がかかります。
たとえば、孫に1,000万円を渡すために、10年かけて100万円ずつ贈与したとします。
一見、非課税で贈与できたように思えますが、税務署に「最初から1,000万円を贈与すると両者で約束されていた」と判断されると、1,000万円から110万円の基礎控除額を差し引いた890万円に贈与税がかかることになります。
よって、贈与するごとに贈与契約書を交わし、贈与する時期や金額を一定にしないなど、財産の渡し方には注意が必要です。
また、祖父母が孫名義の口座を開設し、孫のために預金しているようなケースがよく見受けられますが、これは名義預金になる可能性が高いので注意しましょう。
名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者が異なる預金を指し、税務署に名義預金と判断されると、祖父母の財産として相続税の対象になります。
2.教育資金の一括贈与の特例を適用する
教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の子どもまたは孫が、父母または祖父母から教育資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。
具体的には、以下のような費用が教育資金として認められます。
・入学金・入園料
・授業料・保育料
・施設設備費
・入学・入園の試験料
・学用品の購入費
・修学旅行費
・学校給食費
・習い事の費用 など
制度を利用するときは、専用の口座を開設し、教育資金非課税申告書を口座を開設した金融機関に提出する必要があります。
注意点として、贈与した人が契約期間中に亡くなった、また契約終了時に資金が残っている場合、相続税または贈与税がかかります。
よって、特例を利用するなら早いうちに、また使いきれる金額だけを贈与しましょう。
教育資金が必要なタイミングで都度贈与する場合は、そもそも贈与税がかかりません。
祖父母を含む扶養義務者が教育資金を負担することは当然であるためです。
3.結婚・子育て資金の一括贈与の特例を適用する
結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、18歳以上50歳未満の子どもまたは孫が、父母または祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合に、1,000万円(結婚資金は300万円)までは贈与税が非課税になる制度です。
具体的には、以下のような費用が結婚・子育て資金として認められます。
・挙式・婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃・敷金等の新居費用(一定の期間内に支払われるもの)
・不妊治療費
・妊婦健診費用
・分娩費用
・産後ケアの費用
・子どもの医療費
・保育料(ベビーシッター代を含む)など
制度を利用するときは、専用の口座を開設し、結婚・子育て資金非課税申告書を口座を開設した金融機関に提出する必要があります。
また、教育資金の一括贈与の特例と同じく、贈与した人が契約期間中に亡くなった、また契約終了時に資金が残っている場合、相続税または贈与税がかかる点には注意しましょう。
4.住宅取得等資金の非課税の特例を適用する
住宅取得等資金の非課税の特例とは、子どもまたは孫が、父母または祖父母から住宅を取得するために金銭の贈与を受けた場合に、最高1,000万円までは贈与税が非課税になる制度です。
省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円、該当しない場合は500万円までと住宅によって限度額が異なります。
注意点として、贈与される人や住宅を取得する時期など細かい要件があり、使い方を間違えると利用できなくなるため、事前に税理士と相談することをおすすめします。
5.相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度とは、18歳以上の子または孫が、60歳以上の父母または祖父母から財産の贈与を受けた場合に、2,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。
令和6年1月1日から相続時精算課税にも年110万円の非課税枠(基礎控除)が設けられています。
ただし、贈与した人(父母または祖父母)が死亡したときは、贈与した財産の合計額から年110万円を差し引いた金額が相続税の対象になります。
また、一度選択すると取り消せないなどのデメリットがあるため、制度を利用するときは税理士と相談したうえで判断しましょう。
孫に財産を相続させるときの注意点
孫に祖父母の財産を相続させるときは、以下2点に注意しましょう。
・他の相続人とトラブルになる恐れがある
・孫にかかる相続税が高くなる場合がある
他の相続人とトラブルになる恐れがある
孫に祖父母の財産を相続させることで本来の法定相続人(祖父母の子ども)の相続分が減ってしまうため、家族内でトラブルが起こる恐れがあります。
また、他の相続人の遺留分(最低限の相続分)を侵害してしまうと、より関係性を悪化させることにもなりかねません。
事前に家族で話し合い、財産を残す人も相続する人も全員が納得できる形で進めましょう。
孫にかかる相続税が高くなる場合がある
代襲相続が発生しているケース以外で、孫が祖父母の財産を相続(遺贈)すると相続税が2割加算されます。
通常、親から子に、子から孫に、と相続税がかかるタイミングは2回ありますが、養子縁組により祖父母から孫に財産を引き継がせれば、相続税がかかるタイミングが1回になり、公平ではなくなるためです。
相続税額の2割加算は、被相続人の配偶者、被相続人の父母、被相続人の子ども以外の人が対象になります。
▼相続税額の2割加算の対象になる
・遺言書を作成して孫に財産を相続(遺贈)させるケース
・孫養子に財産を相続させるケース
・孫が生命保険金を受け取るケース
▼相続税額の2割加算の対象にならない
・孫が代襲相続人になるケース
また、孫が財産を相続(遺贈)した場合や生命保険金を受け取った場合は、生前贈与加算の対象になる点にも注意しましょう。
生前贈与加算とは、相続が発生する前の3〜7年以内に贈与した財産が相続財産として加算されることです。
加算の対象になると、贈与税は非課税でも結果的に相続税が高くなる場合があるため、生前贈与は早いうちから計画的に実行しましょう。
相続財産が3億円を超えるようなケースでは、孫に財産を相続させたほうが家族全体の相続税額が抑えられる可能性があります。
状況によってメリット・デメリットは異なるため、1円でも相続税の負担を抑えるためにも相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
【Q&A】孫への相続に関するよくある質問
ここからは、孫への相続に関するよくある質問にお答えします。
孫への相続はいくらまでなら非課税?
祖父母の遺産総額が相続税の基礎控除額以下なら、相続税は非課税です。
相続税の基礎控除額は、以下で計算します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
いくらまで非課税かを知りたい場合は、まず基礎控除額を計算してみましょう。
相続税の基礎控除を詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。
相続税の基礎控除を税理士がわかりやすく解説
孫の相続税はいくらからかかる?
相続税は基礎控除額を超えた金額にかかるため、いくらからかかるかは個々に異なります。
相続税の基礎控除額は、以下で計算します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)になり、祖父母の遺産総額が4,800万円を超えたら相続税がかかります。
親が死亡している場合は孫が相続する?
孫の親(祖父母の子ども)が祖父母よりも先に亡くなっている場合、孫が法定相続人として祖父母の財産を相続することになります。
これを「代襲相続」と呼び、孫は代襲相続人となります。
代襲相続が発生している場合、孫の親(祖父母の子ども)から孫に相続の権利がそのまま引き継がれます。
孫への相続に関するお悩みは税理士法人吉本事務所へ

・かわいい孫に財産を残したい
・できるだけ税金の負担を抑えて財産を渡したい
・相続税対策として養子縁組を検討している
・他の相続人とのトラブルが起こらないように進めたい
など、孫への相続や相続税対策のお悩みは税理士法人吉本事務所にご相談ください!
当事務所では相続専門の税理士が、相続税・贈与税の申告をはじめ、生前対策、遺言書作成など、各種相続手続きのご相談やご依頼をお受けしています。
長年の経験と知識を活かした相続税対策を強みとし、お客様にとってベストな選択をご提案いたしますのでどうぞご安心ください。
また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、内縁関係の相続に関する幅広いお悩みに対応可能です。
お忙しい場合はオンライン相談もお受けしているので、まずはお気軽に税理士法人吉本事務所までお問い合わせください。
当事務所のホームページはこちらから
無料お見積り・お問い合わせはこちらから
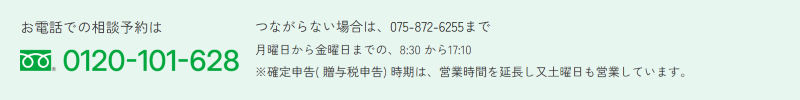
まとめ
孫は原則として、祖父母の法定相続人にはなれないため、遺言書を作成するまたは孫と養子縁組をするなど生前の対策が必要です。
ただし、トラブルが起きたり余計な負担が増えたりする可能性もあるため、相続専門の税理士に相談しながら確実に孫へ財産を引き継がせる方法を検討していきましょう。